自動車ジャーナリストはもはや「不要」なのか? 偏向&懐古趣味がネット時代の読者に響かない根本理由
- キーワード :
- 自動車
ネット自動車論争の実像

筆者(三國朋樹、モータージャーナリスト)は先日、当媒体で「あなたの「クルマ愛」、本当に健全? 匿名空間で暴走する「口うるさい自動車ファン」の正体」(2025年9月16日配信)を執筆した。
記事では、ChatGPTに「ネット上で声の大きい自動車ファンの特徴」と入力したところ、興味深い七つの項目が返ってきた。筆者の経験から見ても、「あるある」と頷く要素が多い内容だった。ネット上で存在感を強める声の大きい自動車ファンの行動や心理を整理できる材料となった。七つの特徴を改めて書くと、
・強いブランド嗜好と信仰的態度
・「正しい知識」の独占欲
・スペック至上主義
・排他性・優越感
・ネット特有の攻撃性
・実体験との乖離
・承認欲求とコミュニティー依存
である。これらは、所有や試乗経験の有無に関係なく、ブランドや技術知識への傾倒を武器に、ネット上で自分の意見を正当化する行動として現れる。過激な書き込みや論争を誘発する場合もあるが、一方で車種や技術に関する検証を促す契機となることもある。
支持されぬ記者像検証
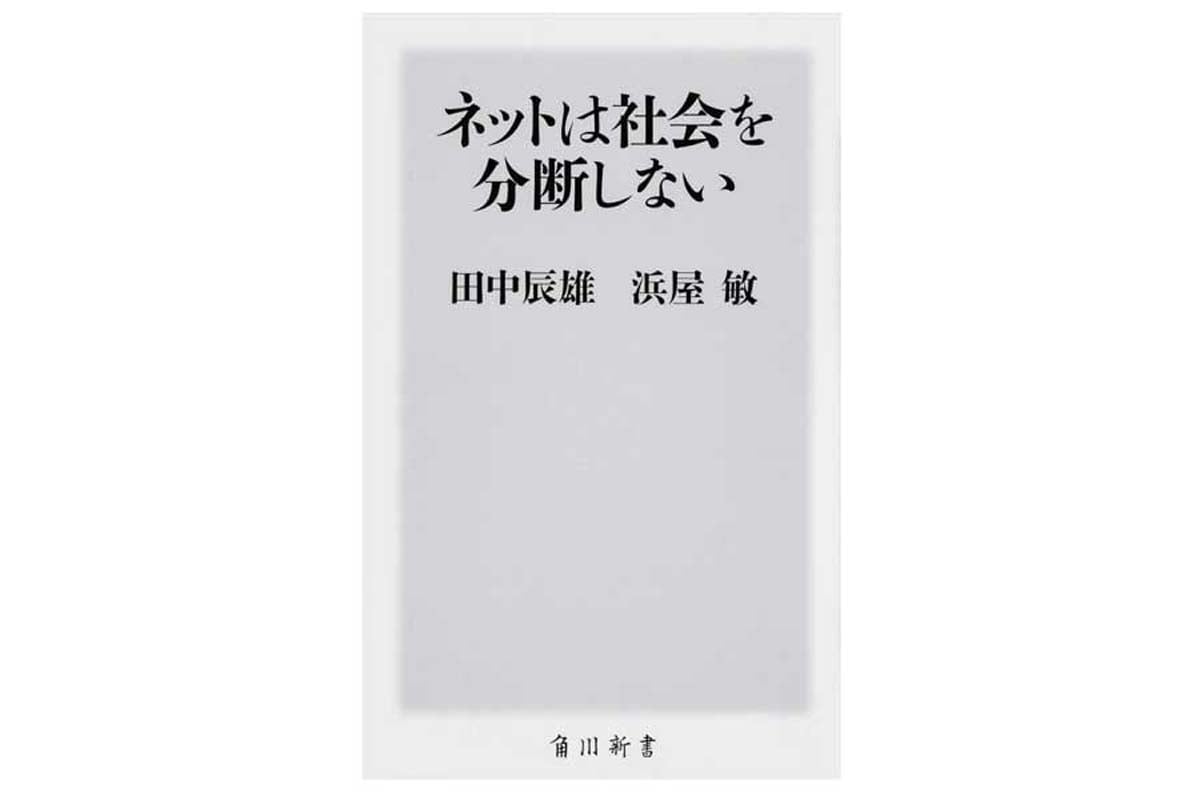
過去にネット全体を対象とした10万人規模の調査(ネット全体であり、自動車ファンだけでない)では、ネット上で過激になりやすい層は
「高齢者」
であり、投稿の「約半数」は
「0.23%(435人にひとり)」
の少数人によるものであることがわかっている(田中辰雄、浜屋敏)。また、SNSではタイトルだけで情報が拡散され(SNSユーザーの59%)、正確性が低下しやすい傾向もある(2016年米国調査)。こうした背景を踏まえると、過激な書き込みの影響範囲や頻度を冷静に把握し、消費者やファンの判断力を支える仕組みを構築することが重要である。
さて、配信先の「carview!」には100件以上のコメントが寄せられた。そのなかには、この特徴は
「自動車ジャーナリストにも同様の非難が当てはまるのではないか」
という指摘もあった。こうした声を踏まえ、筆者は今回、
「ネット上で支持されない自動車ジャーナリストの特徴」
についても検証することをテーマとした。理由は明確だ。ネット上で支持されないジャーナリストの存在は、情報発信の信頼性や議論の健全性に直接影響する。声の大きいファンや情報受け手が、ジャーナリストの評価や発言内容をどのように受け止めるかを把握することは、消費者保護やメディア運営の視点からも重要である。
本稿では、同様にChatGPTを活用し、「ネット上で支持されない自動車ジャーナリストの特徴」を出発点に、各項目を確認・考察する。ChatGPTは、大量のテキストデータを学習した人工知能である。質問内容に基づき、過去の事例やパターンから最も妥当と思われる情報を統計的に抽出・整理して回答を生成する。内容は、ネット上の議論や自動車ファンの行動に関する膨大な文献や投稿の傾向を反映したものである。つまり、単なる筆者の印象や主観ではなく、広範なデータに基づく合理的な整理であると評価できる。