国民は「JR」から鉄道を取り戻すべき? コロナ禍で浮き彫りになった国鉄民営化の功罪! 自治体「発言権強化」の必要性を考える
初乗り運賃200円で鉄道改革
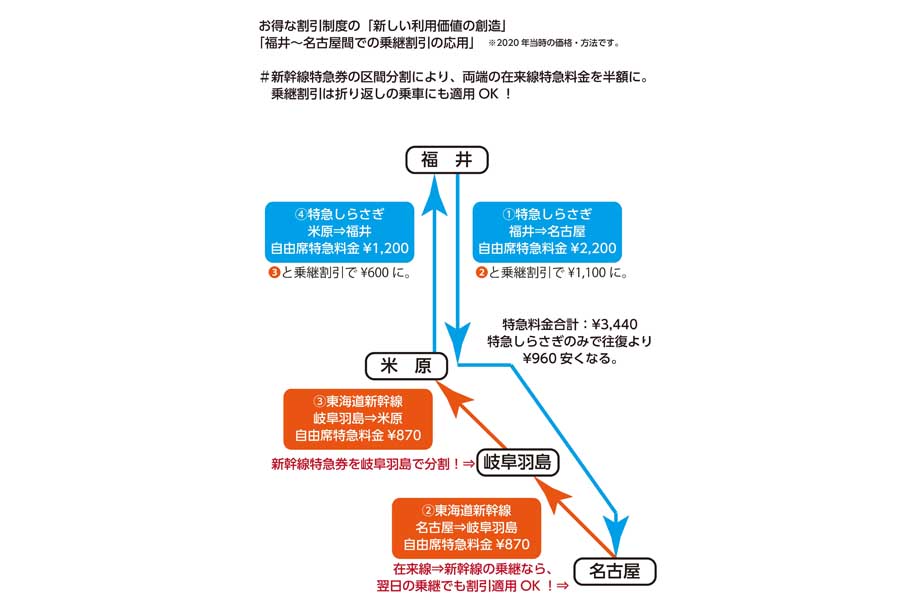
都市部の運行経費削減や、赤字線区の運行を維持するための鉄道事業者への支援が検討されるべきだ。鉄道事業者に配慮した政策が求められている。
例えば、JRと自治体が共同出資するローカル線会社の設立は有効な選択肢だ。富山県では、分離された北陸本線や周辺の氷見線、城端線、高山本線などを自治体と第三セクターが運営する動きが見られる。このような取り組みは、全国の都道府県で奨励される可能性がある。JRが首都圏以外の在来線を自治体に譲渡することで、助成金の受けやすさや、地域おこし協力隊などを活用した運営コストの抑制が期待できる。ローカル線の維持には、京葉線のような一部都市鉄道も対象にし、地域おこし協力隊の雇用期間延長も視野に入れるべきだ。
次に、鉄道の初乗り運賃をバスと同じ200円台に引き上げる提案がある。JR東日本が都内で運賃値上げを実施したことが話題になったが、山手線などの減便に伴う混雑を緩和するために、初乗り運賃を200円程度に設定する案もひとつの方法かもしれない。この変更により、1駅だけの利用が減り、バスや自転車への転換や徒歩移動が増えることが期待される。また、近距離の客単価向上分を遠距離運賃の引き下げに充てることができれば、例えば東急電鉄のような鉄道ネットワークでは均一料金200円で全線を維持し、収益改善が見込まれる。
鉄道事業者の立場を考慮すると、1駅から1両分ずつ乗客が乗る場合、ターミナル駅手前の最後の区間を運行するために始発駅から輸送力を投入するが、その費用は1駅利用者の運賃には転嫁されていない。この点を踏まえ、都市圏内では均一またはそれに近い運賃制度を認めるべきだろう。その代わり、シニアSuicaやヤングSuicaを導入し、1乗車あたり100円引きとすることで、高齢者や中学生などの負担軽減にもつながる。
さらに、鉄道業界を含む全業界において、6時間以上勤務した場合に最低日当1万円、有資格者には最低日当1万5000円を義務付けることが重要だ。この問題は鉄道業界に限らず、全体的な労働環境の改善に寄与する。例えば、熊本では運転士不足で減便が発生したが、資格を持った人々が続けたくないという現状もある。そこで、6時間を超える勤務には休憩時間を設けるように、最低日当を設定することが検討されるべきだ。また、赤字ローカル線への補助金も、最低日当を考慮して支給されることが望ましい。