国民は「JR」から鉄道を取り戻すべき? コロナ禍で浮き彫りになった国鉄民営化の功罪! 自治体「発言権強化」の必要性を考える
鉄道ダイヤ改正やサービスの変化は、コロナ禍を経て地域経済に深く関わる課題が浮き彫りになり、自治体との連携強化が求められている。民営化された鉄道事業は、利益重視から地域密着型への転換が必要で、京葉線の通勤快速廃止問題など、住民生活に対する柔軟かつ迅速な対応が重要となっている。
新幹線活用で渋滞緩和
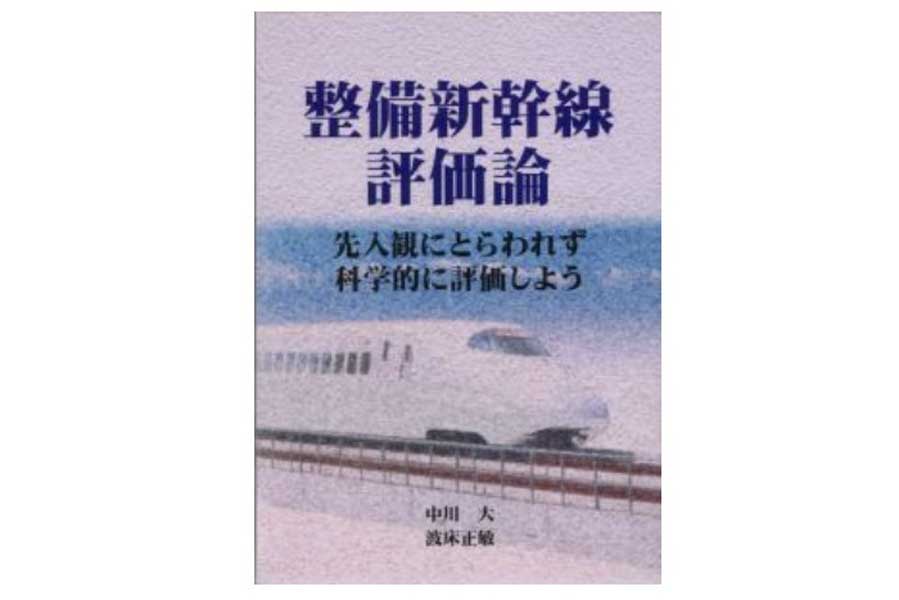
2020年代後半に議論すべき政策としていくつか提案したが、それぞれに対する意見もある。
まず、鉄道行政専門職員の配置について、神谷俊一千葉市長は、「年に1回のダイヤ改正のために常勤雇用は現実的でなく、鉄道事業者への要望活動の場や研究会などで臨時雇用による活用に限定される」との考えを示している。
都市圏運賃200円均一化については、交通評論家の佐藤信之氏が負担の公平性について疑問を呈した。
また、ある鉄道市民団体からは、線路特定財源の創設よりも道路財源を活用する方がよいとの意見があった。その根拠として、新幹線整備により、高速道路や高速バスからの利用者の転移が一定の規模で起きていることが挙げられている。
中川大と波床正敏の著書「整備新幹線評価論」(ピーテック出版部)によれば、300~400kmの移動において、新幹線が利用可能な場合、車の利用割合は60%から20%に減少するとしている。このデータを踏まえると、高速道路の渋滞対策として、道路財源を新幹線整備に活用するのもひとつの現実的なアプローチかもしれない。
2020年代の折り返し地点から過去5年間を振り返ると、鉄道分野においてさまざまな課題が浮き彫りになってきたように感じる。これらの課題は、以前から存在していたが後回しにされてきた部分も多い。これからは、より本質的な議論を深め、鉄道分野にとって前向きな方向へと進むために、皆で取り組んでいけるとよいだろう。