国民は「JR」から鉄道を取り戻すべき? コロナ禍で浮き彫りになった国鉄民営化の功罪! 自治体「発言権強化」の必要性を考える
鉄道ダイヤ改正やサービスの変化は、コロナ禍を経て地域経済に深く関わる課題が浮き彫りになり、自治体との連携強化が求められている。民営化された鉄道事業は、利益重視から地域密着型への転換が必要で、京葉線の通勤快速廃止問題など、住民生活に対する柔軟かつ迅速な対応が重要となっている。
反対意見に揺れる新幹線計画
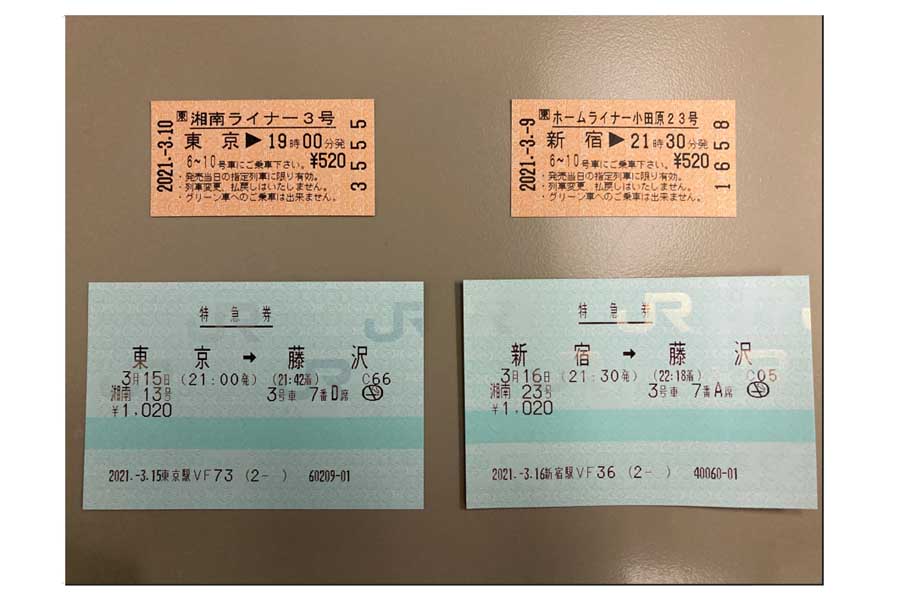
整備新幹線事業は現在、重要な転換点に差し掛かっていると言える。2022年に西九州新幹線が部分開業し、2024年には北陸新幹線敦賀延伸が実現したが、その後の開業計画についてはまだ具体的な進展は見られない。西九州や北陸地域では、中心都市から離れた沿線自治体が新幹線の整備に反対する傾向が見られる。
例えば、佐賀県、滋賀県、京都府などがその例にあたる。これらの地域は、すでに別の新幹線が通っていたり、中心都市に近いため、費用負担に見合うメリットを感じにくいという理由がある。このように、2020年代前半は整備新幹線事業が制度疲労に直面していた時期と言えるだろう。
そのなかで、北陸新幹線の小浜ルートについては強引な誘導が問題視され、整備新幹線ルートの議論においても同様の誤りが繰り返されるのではないかという懸念がある。
北陸新幹線のルート問題については、筆者が国の試算が米原ルートを不利に見せるために数字を操作していた点を指摘し、また他の専門家や地元政治家からも小浜ルートへの異論が広がっていることが明らかになっている。
最近では、「米原ルート議論は雑音だ」といった過激な意見も出てきている。しかし、もしJRの主張をそのまま受け入れ、北陸新幹線ルートの再考が行われないのであれば、整備新幹線の議論で再度誤りを犯すことになるかもしれない。