徳川家康が死を覚悟した「神君伊賀越え」 400年前の“逃避行”をご存じか【連載】江戸モビリティーズのまなざし(12)
- キーワード :
- 江戸モビリティーズのまなざし, モビリティ史, 徳川家康
江戸時代の都市における経済活動と移動(モビリティ)に焦点を当て、新しい視点からそのダイナミクスを考察する。
大河ドラマを誘致する自治体
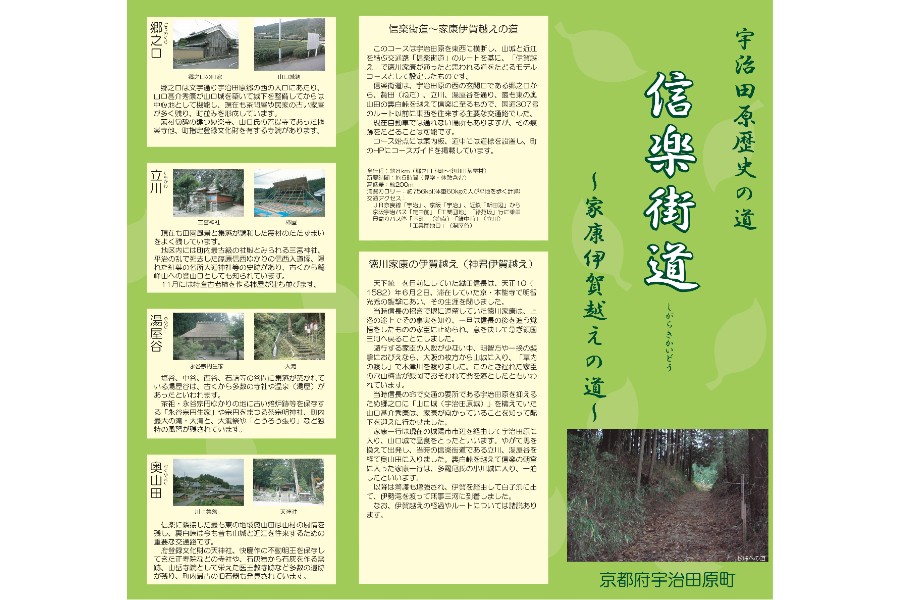
大河ドラマの経済効果は、地域起こしの起爆剤のひとつだ。
『どうする家康』の経済効果については前述したが、昨年の『鎌倉殿の13人』でも神奈川県全体で約307億円(横浜銀行/鎌倉市観光協会調べ)、伊豆の国市で約16億円(伊豆の国市/静岡経済研究所調べ)と発表されている。
コロナ禍においてさえ、これだけの効果があった。
また、各地で大河ドラマ誘致も盛んだ。現在も、
・楠木正成 大阪府河内長野市ら5府県35市町村
・太田道灌 神奈川県伊勢原市
・三好長慶 徳島県徳島市
などが、誘致推進協議会を組織している。三好長慶の場合は2022年が生誕500年にあたるため、ドラマ1日放映分のストーリーを募集するなどの企画も行ってきた。
他にも後北条五代(神奈川県)、大友宗麟(大分県)、立花宗茂(福岡県)、保科正之(長野県)なども誘致活動が展開されている。いずれも観光振興と、地域経済の活性化が狙いだ。
こうした著名な武将たちは、地域の歴史遺産といっていい。それらを活用することは、新型コロナのダメージが蓄積されて疲弊している地方にとって、今後さらに必要になるだろう。
モビリティに関わる人々も、活用方法を模索したいところだ。