生活道路「30km制限」は本当に正しいのか?――人命優先か過剰規制か、制度の歪みを問う
2026年9月、生活道路の法定速度が60kmから30kmに引き下げられる。東京都では歩行者死亡事故の約40%が占めるなど、速度が安全に直結する現実を踏まえ、全国一律改定の背景と課題を検証する。
道路構造の更新
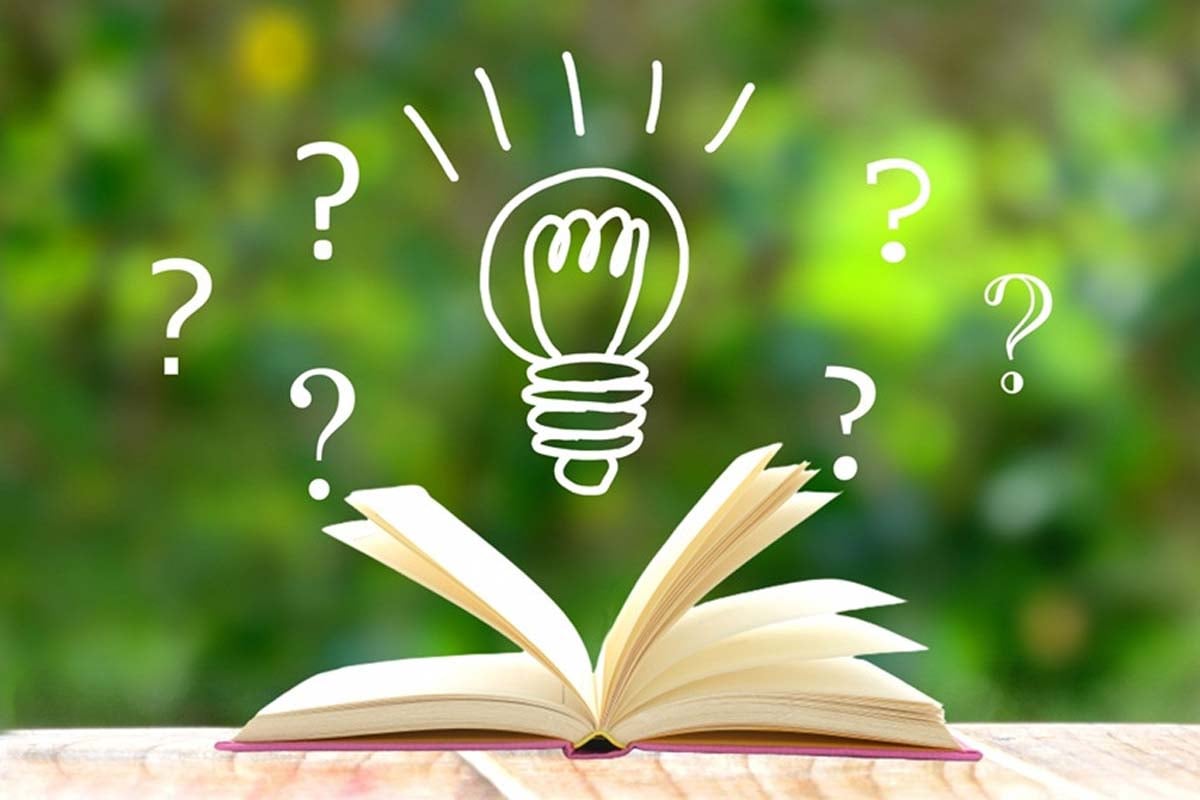
法定速度の引き下げは、安全を優先する政策として正しい。しかし、その前に整備すべき課題はいくつも残っている。標識や道路表示の設置、信号や道路構造の整備、歩車分離や自転車専用レーンの整備など、取り組むべきことは多い。
今後、よりよい交通社会を築くために必要な方向性を整理すると三点にまとめられる。
まず道路分類の見直しである。都市部や準都市部、農村部など地域ごとに交通量や道路構造は異なる。そのため、地域に応じた速度基準を設定することが必要だ。今回の改定では中央線の有無で区別されるが、歩行者や自転車の交通量も考慮した区分の仕組みづくりが望まれる。
次に道路構造の更新だ。日本の道路はまだ完全に整備されているとは言えない。道路幅の拡張、中央線や縁石の設置、歩行者・自転車・自動車の完全分離、照明や標識の適切な配置など、物理的な環境の整備が不可欠である。速度を制限するには、こうした基盤整備があって初めて効果を発揮する。
最後に交通情報のデジタル統合だ。近年の技術進化により、自動車ナビや信号制御、警察や国土交通省のデータを連携させ、リアルタイムで最適な走行速度を提示する可変速度制御が可能となっている。こうしたシステムを活用すれば、利用者に合わせた円滑で安全な交通環境が実現できる。ただし、利用者側も新しい速度制限に対応できる知識と技術を身につける必要がある。