生活道路「30km制限」は本当に正しいのか?――人命優先か過剰規制か、制度の歪みを問う
2026年9月、生活道路の法定速度が60kmから30kmに引き下げられる。東京都では歩行者死亡事故の約40%が占めるなど、速度が安全に直結する現実を踏まえ、全国一律改定の背景と課題を検証する。
法定速度の歴史
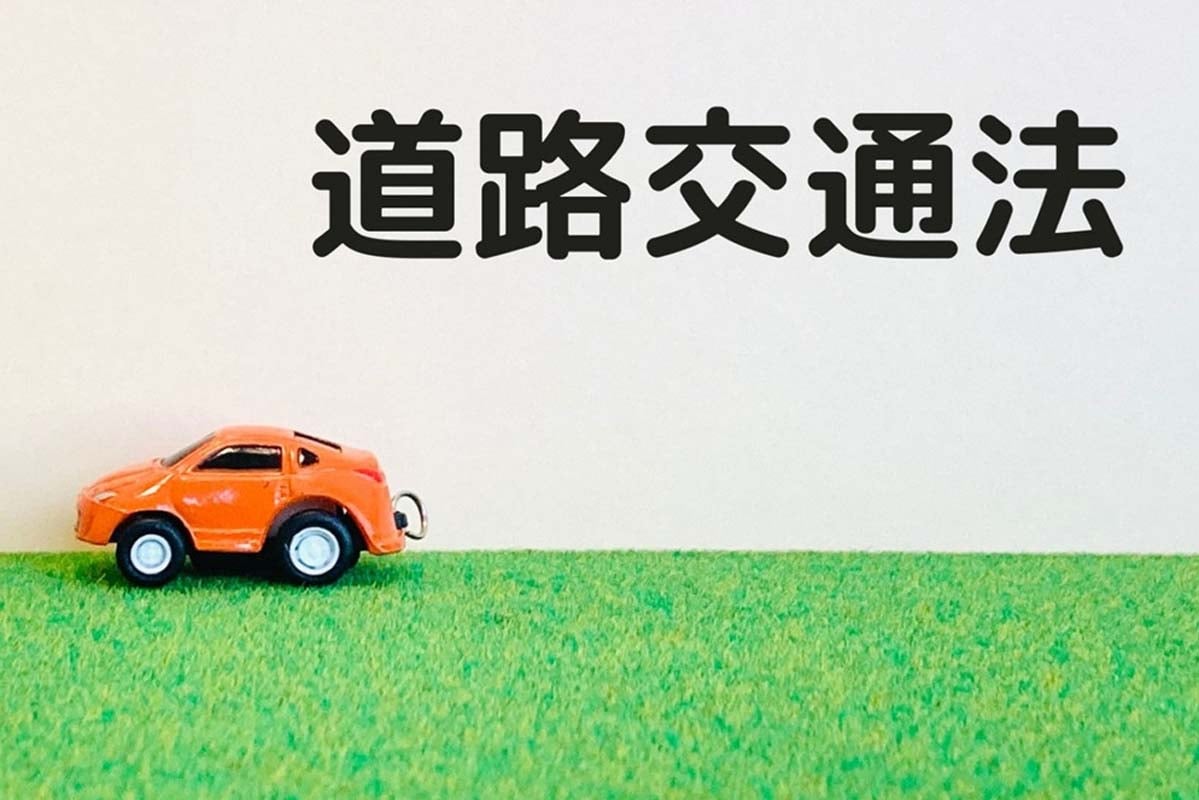
現在、一般道の法定速度が60kmに設定されたのは、戦後の1960(昭和35)年に制定された道路交通法である。これより低い速度が望ましい道路や区間には、制限速度が設けられている。制限速度は過去に何度か議論や交通調査を経て、社会状況や交通実態に応じて変更されてきた。
法定速度そのものも、1912(明治45年、大正元)年に日本初の自動車規制が定められた際は16kmであった。その後、自動車の性能や社会情勢の変化に合わせて改定されてきたが、1960年の道路交通法制定以降、大きな変更はなかった。そのため、人口増加や住宅街・生活道路の拡大が進む現代日本で、
「中央線のない道路 = 60kmで走行可能」
という設定は、実態と大きく乖離しているといえる。
一方で、生活道路という用語は存在するが、法律上の正式な定義はない。どの範囲を生活道路と呼ぶのかは明確でなく、行政管理や警察管轄で認識や判断に不一致が生じやすい。さらに地方では、通勤通学や地域生活が主な目的の道路や農道も多く、都市部の幹線道路やバイパスに比べ整備が遅れている。
これらの道路も生活道路に区分されると、日常生活への影響が懸念される。今回の改定が都市部と地方部の実情の違いを十分に考慮しているかには疑問が残る。