バス業界を変革するカギは「スペシャリスト採用」だ! 昔ながらの“何でも屋”育成システムの脱却を
筆者の意見

バス業界は、単純に事務職や運転職、車両整備といった技術職を雇えばよいわけではない。本来、業界が抱える課題には、
・労務管理
・交通関係法
・環境問題
・福祉関連の知識
を持った専門職が必要だ。しかし、現在の採用慣行では、専門職が積極的に採用されていないのが現実である。多くの企業はジェネラリストを採用してしまい、この状況では業界の進化は期待できない。
筆者が身を置く大学業界では、近年、事務系の専門職を積極的に採用している。例えば、
・教職員のキャリア形成
・知的財産
・法務
・研究支援
・データサイエンス
など、多くの専門家が教員とともに大学の運営に携わっている。専門職の強みは、各分野に関する深い知識と経験を持ち、問題解決に誇りを持って取り組む姿勢だ。
では、バス業界はどうか。現状では、職員が本社から営業所に異動したり、逆に営業所から本社に異動したりするなどのパターンが多い。これが悪いとはいわないが、バス業界が厳しい状況にある今、各分野の専門家が集まり、ときには連携し、ときには切磋琢磨(せっさたくま)しながら、業界の未来を模索する雰囲気を作ることが必要だ。
また、公共交通分野での専門家を目指す大学院修了者のなかには、
「もっと事業者が採用してくれれば、自分の力を発揮できるのに」
という声もある。
専門知識でバス業界を革新
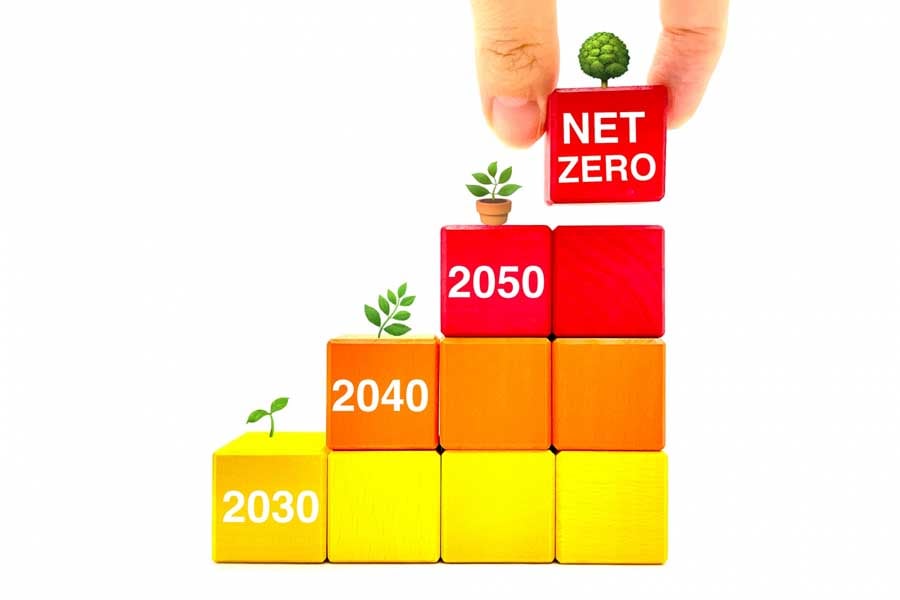
現在のバス業界は、2024年問題を背景に、運行の労務管理や安全性の向上において、専門家による制度設計や規制順守が欠かせなくなっている。
また、
・エネルギー問題への対応
・ゼロカーボンの推進
に関しても、環境問題を無視することはできない。環境への配慮が求められる現代において、バスの運行を環境的に持続可能な方法へとシフトするための専門的な知識が必要である。
さらに、福祉の観点からは、バリアフリーやユニバーサルデザインを考慮した運行方法や、高齢者や障がい者に対するサービスの向上が求められている。これらの課題に対応するためには、業界が各分野の専門職を積極的に採用し、ジェネラリスト中心の採用慣行を見直すことが重要だ。
専門職を採用すれば、外部の専門家と連携する必要が減り、問題解決が迅速に進むと考えられる。