淡路島と和歌山の「矢印エリア」に、なぜ橋を作らないのか?
紀淡海峡に橋を架ける構想は1960年代から議論され、約11kmの海峡横断は世界最長級の吊り橋計画として注目された。しかし、技術的課題や財政事情、環境問題が重なり半世紀以上実現を見ないままだ。高度経済成長期のインフラ投資熱が冷めるなか、現代の技術と経済状況で再評価が求められている。
所要時間短縮のみの根拠
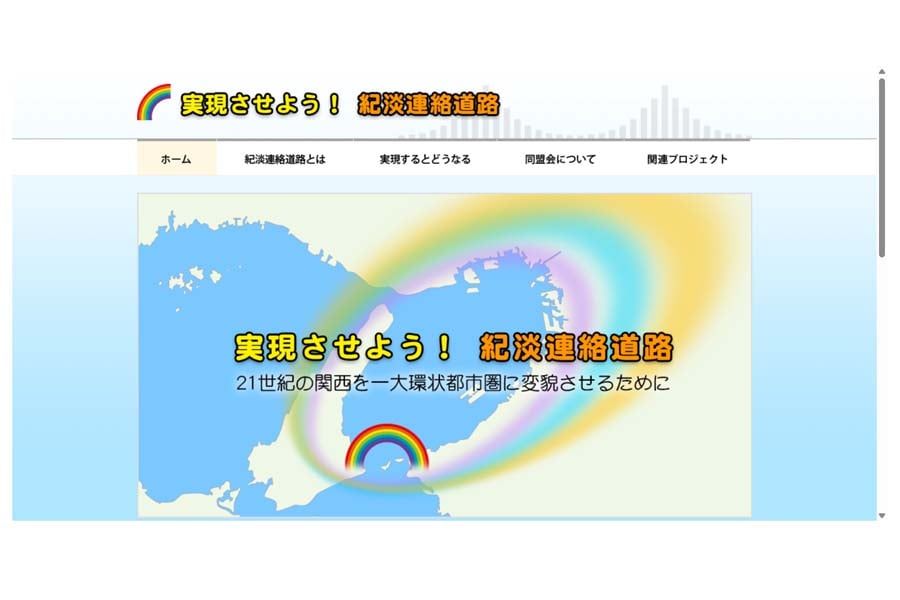
紀淡海峡架橋構想は、「何のために架けるのか」という根本的な意義が曖昧だった。その不在こそが、実現に至らなかった最大の要因である。
興味深いのは、現在も活動を続ける紀淡連絡道路実現期成同盟会の主張が、1990年代当時とほとんど変わっていない点だ。
同会のウェブサイトでは大阪湾環状道路、関西中央環状道路、関西大環状道路の3本を組み合わせた
「関西全体の一大環状都市圏」
構想が掲げられている。だが、そこで語られている効果は相変わらず抽象的だ。
・貨物輸送の増大
・ビジネスチャンスの拡大
・学術交流の活発化
・観光プランの多彩化
といった表現が並ぶ。具体的に示されているのは、都市間の所要時間短縮に関する数値だけである。交通需要の規模、建設に必要な費用、費用対効果の見通しなど、基本的な検討結果は一切提示されていない。
前述のとおり、SNSでは今も「橋があればいいのに」という声が散見される。この種の憧れは今後も続くだろう。しかし、いかに技術が進歩しても、目的が明確でなければ構想は動かない。
紀淡海峡架橋は、あったら便利という段階から一歩も進まなかった構想として、これからも語られ続けるはずだ。