武蔵小杉はなぜ「タワマンだらけの街」になったのか? 住民激増、町内会解散…100年前からの歴史を辿る! 令和の都市開発は成功か失敗か
地価3倍超が示す住宅需要
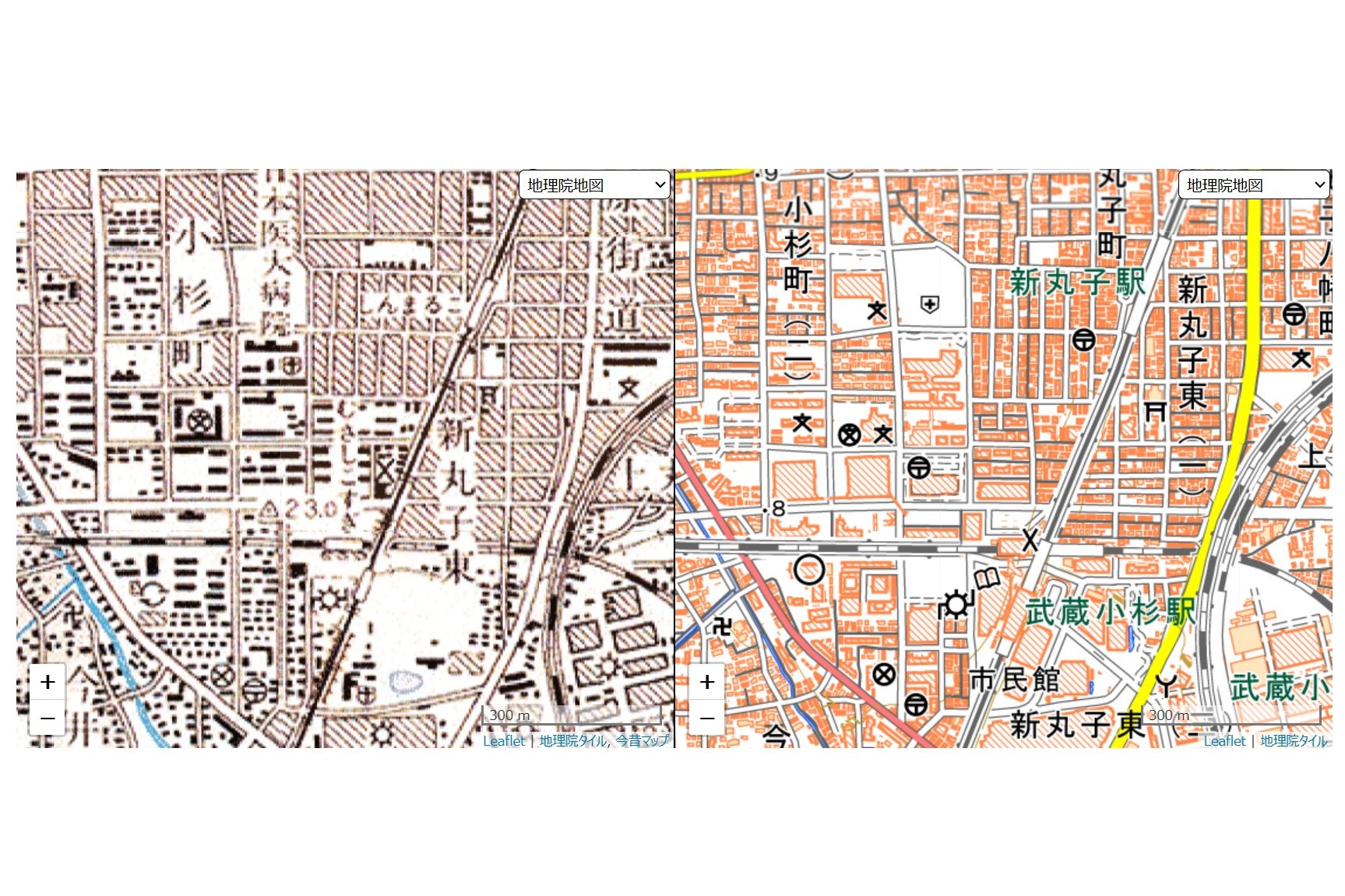
戦後の復興期において、武蔵小杉はすでに首都圏のベッドタウンとして注目されていた。『読売新聞』1956(昭和31)年8月23日付の夕刊では、川崎市中原地区の建築ブームについて詳しく報じている。
記事によると、当時の川崎市では人口50万人突破が目前に迫っていた。市役所が同年1月から8月中旬までに受け付けた住宅の建築許可は約3900戸にのぼった。そのうちの43%が中原地区に集中していた。
住宅の種類はアパートや公営住宅、個人住宅など多岐にわたる。特に個人住宅の増加が顕著だった。記事には「農地は(昨年の)2倍近い早さで減っている」との記述があり、急速に宅地化が進んでいたことがうかがえる。
それと同時に、土地の価値も上昇していた。以下に紹介する記事の一節からは、当時の状況がよく伝わってくる。
「1952、53年ごろの南武線武蔵小杉、中原付近は駅の近所で6~7000円、15分ほど歩いて2000円くらいだったのが、今では同じところがそれぞれ1万円、3500円というところ。昨年住宅公団が7000円ぐらいで買った小杉駅前のアパート用地は今年買えば1万円をはるかに越したろう」
記事では「住宅の建築が市中心部では飽和点に達し、農地を潰して西北部に伸びてきている」と解説されている。この記述から、武蔵小杉の最初のベッドタウン化は、川崎市中心部の人口増にともなって起きた現象だったことがわかる。
1967年になると、武蔵小杉は川崎市でも有数の人口集中エリアに成長していた。『読売新聞』1967年4月13日付朝刊は、「サラリーマンのベッドタウン」として発展する武蔵小杉の姿を報じている。
記事によると、大型スーパーの出店が相次いでいた。それに対抗する形で、地元商店街は団結を強めていた。特に注目すべきは、2路線が交差する武蔵小杉駅周辺に、商店街加盟店舗が170店もあったという点だ。これらの動きは、当時からすでに武蔵小杉がベッドタウンとして大きく発展していたことを物語っている。
その後も武蔵小杉の発展は続いた。『神奈川新聞』1979年12月24日付の「新ショッピング地図」では、
「(川崎市の)真ん中といえば中原区だし、中原区の中心は、この武蔵小杉です」
という声が紹介されている。さらに、川崎市役所が武蔵小杉に“遷都”する計画があるという報道まであった。
これだけ発展と注目を集めた土地だけに、より利便性の高い街を求める声は、かなり早い段階から上がっていたと考えられる。