庶民の生活直撃も 「ガソリン価格」が当面下がらない三つの要因
トリガー条項の発動はあるか?
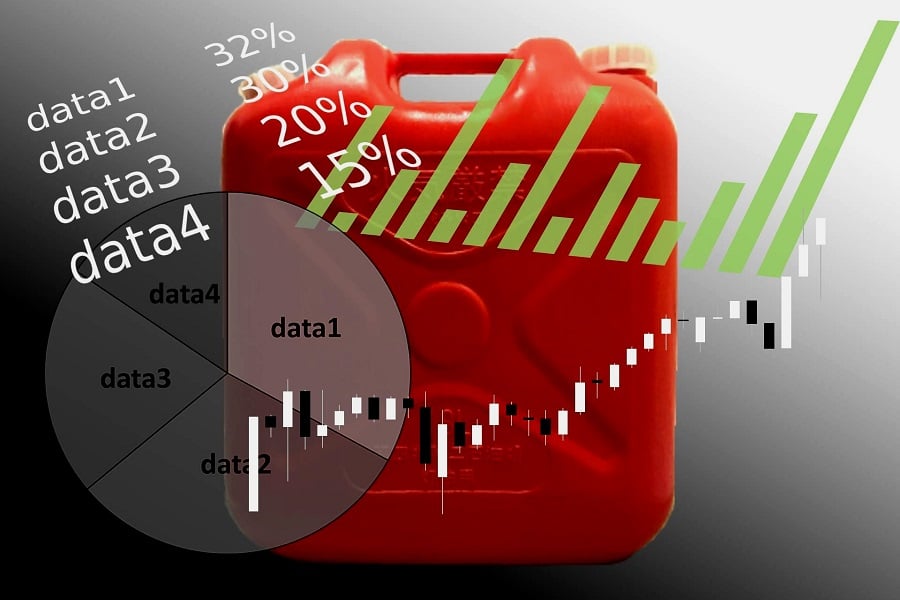
ガソリン価格を構成する二つ目の大きな要素が、ガソリン税である。ガソリンには1l当たり53.8円のガソリン税が課されており、今回のガソリン価格の高騰を受けて、このガソリン税の引き下げを求める国民の声が高まっている。
とりわけ注目されているのが「トリガー条項」だ。トリガー条項とは、ガソリンの全国平均価格が3か月連続で160円を超えた場合、ガソリン税を25.1円引き下げるというものである。 現在、東日本大震災の復興財源確保のためこの条項の発動が「凍結」されているが、岸田首相が2022年2月21日(月)の衆議院予算委員会で凍結解除を含め検討する考えを示したことで、今後が注目される。
首相の政策判断なので、今後を予測するのは困難だが、完全な発動(凍結解除)はかなり厳しいだろう。なぜなら、トリガー条項の発動には法改正が必要で、財政難から議論が難航するからだ。
国の借金が1,218兆円(2021年12月現在)に達し、いま政府・財務省は、国際公約である「財政健全化」の旗印を降ろすかどうかという瀬戸際に追い込まれている。IMFから消費税を2030年までに15%に引き上げるよう勧告を受けている。大規模かつ恒久的な減税は、極めて難しい状況だ。
ガソリン税53.8円は、揮発油税48.6円と地方揮発油税5.2円に分かれる。金子総務相は同月22日(火)に「トリガー条項を発動した場合、地方揮発油税と軽油引取税で地方自治体の税収が1年間で約5000億円以上減る」という試算を公表した。発動には、税収減に直面する自治体との調整が必要になる。
また、世界的に脱炭素化の動きが広がっていることから、各国とも石油需要の増大につながる税制見直しや補助金導入には慎重だ。日本が先陣を切ってガソリン税制を見直すというのは、かなり抵抗感があるに違いない。
以上から、政府がトリガー条項を発動するのは難しい(簡単にできるなら、元売への補助金という奇策を導入する前にやっていたはずではないか)。仮に発動したとしても、財政を大きく悪化させず、国際的な批判を浴びることがないように、非常に小規模な引き下げ、悪い言い方をすると「やりましたポーズ」にとどまると思われる。