JR東海「名松線」に押し寄せる合理化の波! 2度の廃線危機を乗り越えた過去、沿線住民の熱意はいつまで続くのか
何度も押し寄せた廃止の波
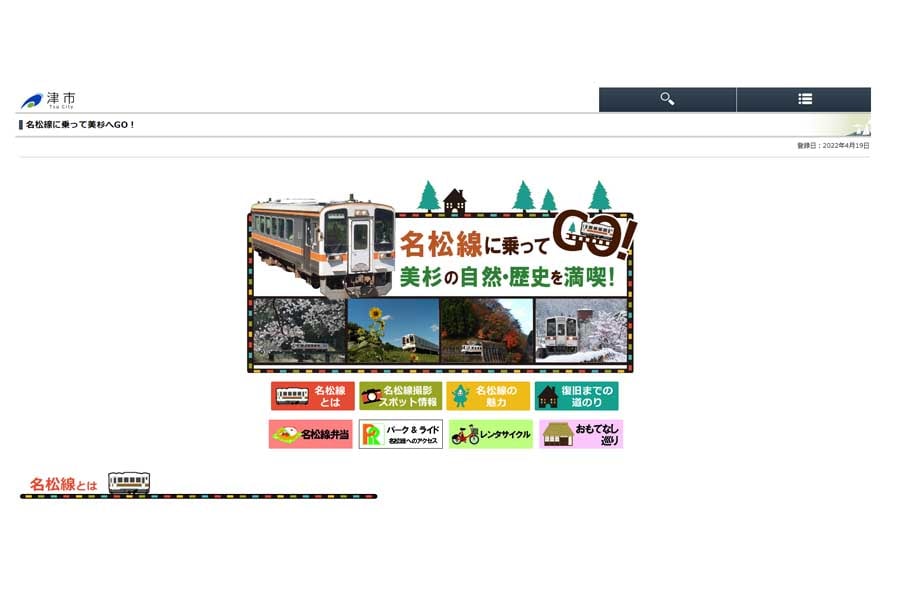
前述のとおり、JR東海は東海道新幹線を抱えているため、赤字路線の損失を黒字路線で埋めることは容易だ。それでも、名松線のような
「走らせているだけで赤字が増えていく路線」
を維持することはふに落ちない。
もともと名松線は松阪と県西部の名張を結ぶ計画だったが、1930(昭和5)年に参宮急行電鉄が現在の近鉄大阪線・山田線にあたる区間を開通させたため、1935年に伊勢奥津駅まで開通して以降、建設は進められなかった。
そんな計画倒れの路線ゆえ、国鉄時代には「赤字83線」のひとつとして廃止勧告対象になった。ところが、三重県の山間部に位置し、道路整備が進んでいなかったため、バスへの転換は困難とみられ、廃止は回避された。また、1982年の台風被害で全線が不通なった際にも、廃止が計画されたが、
・反対運動
・道路事情の悪さ
から、申請は取り下げられた。
そんな路線に再び危機が訪れたのは、2009(平成21)年だった。同年10月の台風18号で、名松線の家城~伊勢奥津間(17.7km)は38か所で土砂崩れが発生。JR東海は
「復旧させたとしても大きな被害が起きる恐れがあり、鉄道による安全で安定的な輸送はできない」
として、不通区間のバス転換の方針を打ち出した。
このときに明らかにされた名松線の収支は、1日あたりの利用者数は700人だった。年間収益約4000万円に対して、維持管理費は約8億円。都合、
「約7億6000万円」
の赤字を積み重ねていた。もはや維持は現実的でないとされ、多くのマスコミも
「名松線一部廃止へ」
「消える終着駅」
と、廃止を確定事項として報じていた。
山と川に挟まれた狭い地形を走る名松線は線路の安全を担保できる治山治水が困難として、JR東海はバスの方が安全・安定輸送ができると理解を求めた。対して、沿線住民は津・松阪の両市までの全線復旧を求めた。