「救急搬送」の遅れが命を奪う――事故率0.01%も「到着遅れ」が示す制度的課題、愛知県男性死亡から考える
愛知県春日井市での救急車とトラック接触事故は、搬送遅延により77歳男性が死亡する事態に発展した。2024年度には救急搬送の63%が高齢者で、出動は約4.1秒に1回のペースに達しており、官民連携によるAI・交通インフラ活用の再発防止策が急務である。
トラック停止困難事故
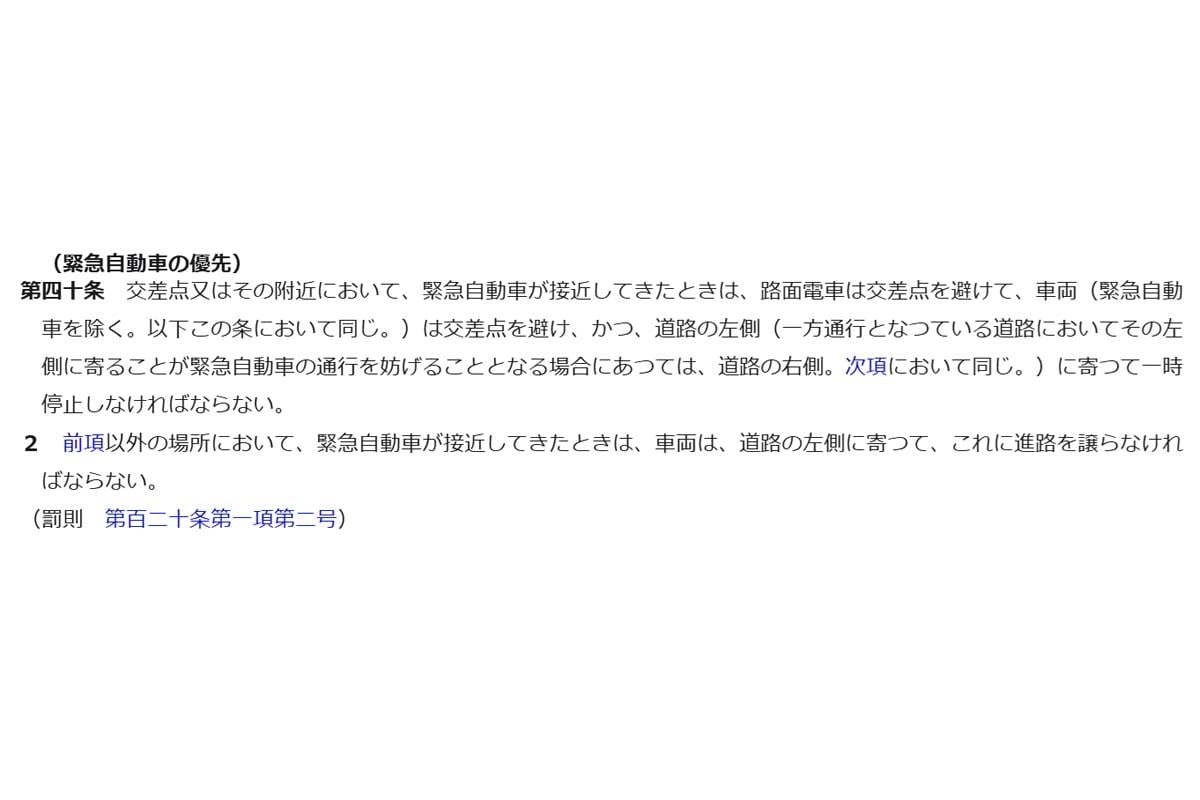
道路交通法第40条は、緊急自動車の優先について具体的に定めている。
サイレンや赤色灯を点灯した緊急自動車が接近した場合、すべての車両や路面電車は交差点を避け、道路左側に寄って一時停止しなければならない。一方通行の道路では、左側に寄ることが通行を妨げる場合に限り、右側での停止も認められる。今回の片側1車線道路での事故でも、原則としてこれに従うことが求められるが、トラックは左側に寄ることが困難な状況にあった可能性が高い。
2023年度の統計では、救急車が119番通報を受けて現場に到着するまでの平均時間は約10分であり、年々増加傾向にある。そのため、代替の救急車も到着まで時間を要したと考えられる。救急需要は
・高齢化
・不適正利用
の影響で増大しており、出動状況はひっ迫している。加えて、病床やスタッフ不足により搬送先が確保できないケースも顕在化している。これらはいずれも搬送者の死亡原因の一因となり得る。
一方で、内閣府の調査では、緊急自動車接近時に「道を譲っている」と答えたドライバーは98%に上る。また、救急車の事故発生率は出動10万件に対して
「約0.01%(13.9件)」
であり、日本のドライバー全体の交通法遵守率は非常に高いといえる。今回の事故は極めて稀なケースだが、救命率向上のため、早急な再発防止策の検討が求められる。