意外と知らない? 世界的半導体メーカーが「熊本」にわざわざ上陸する理由
地政学的に見た九州・熊本の有利さ
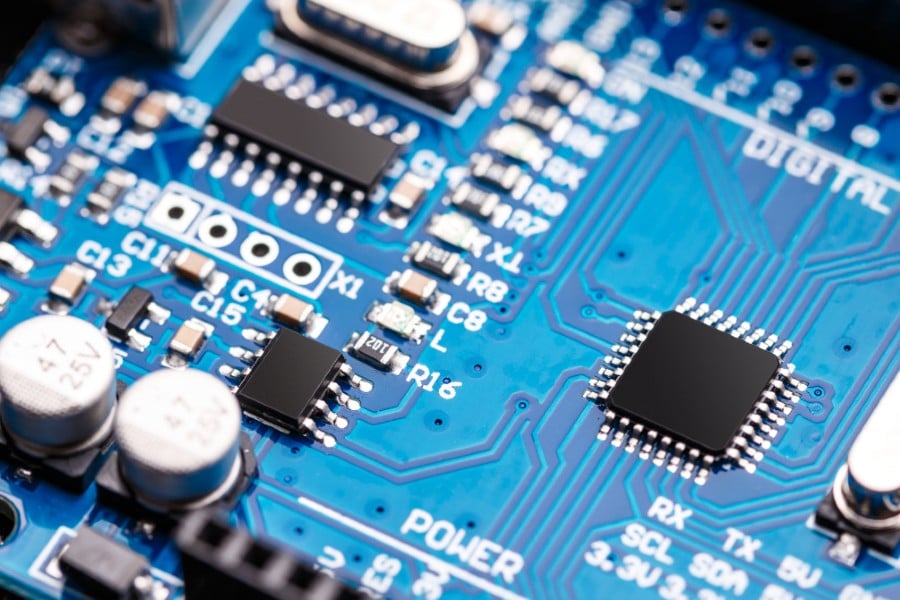
いま、九州、特に熊本県が半導体で盛り上がっている。台湾の世界的半導体メーカー・台湾積体電路製造(TSMC)の工場誘致が決まってから、熊本県が熊本空港と熊本駅を結ぶ鉄道アクセスの整備を発表し、熊本大学が「半導体学部」の新設を予定するなど、ローカルニュースは半導体関連ニュースで持ち切りだ。
工場を誘致すると、台湾からはTSMCの従業員とその家族、合わせて約600人が来日する見込みだという。地元経済に与える影響は大きいが、そもそも、なぜいま半導体なのだろうか。
まずは、地理的な面から見てみよう。
製造業がさかんな九州で、大きな割合を占めるのが半導体産業だ。日本の工業エリアは東京や名古屋、大阪圏に集まっているが、九州への企業進出は1990年代から増加傾向にある。
九州は中国や東南アジアに近く、地価が安い。震度6以上の地震に見舞われる可能性も他エリアに比べて低いとされ、生産拠点や原材料・部品の調達先として、外資系企業の進出も増えているのだ。
そんな九州の中心に位置するのが熊本である。九州を南北に走る九州縦貫自動車道によって、福岡や鹿児島へもアクセスしやすい。
熊本から半径1500kmには、世界トップレベルの企業が集結している。地図に落とし込んでみると、近年国内でもシェアを広げつつある電気自動車(EV)の生産に欠かせない半導体や車載電池、その他の主力部品をつくる会社は、その円の中に収まっていることが分かる。
半導体関連企業が熊本に集まっている理由のひとつは、水にあるといってよいだろう。半導体製造には純度の高い水が必要だが、熊本はその条件を満たす。
実際のところ、阿蘇山を望む熊本地域をはじめ、熊本県の生活用水の8割は地下水だ。今後の気候変動の影響を考えると、水資源が豊富な地域に生産拠点を置くメリットは大きい。
加えて九州は、太陽光や地熱など再生可能エネルギーに恵まれている。そうした好条件から、1960年代以降、数多くの半導体関連企業が進出してきた。