「完璧主義の呪縛」に捕らわれた日本車メーカー bZ4X開発5年 vs SEAL18か月という現実――構造的遅延を断てるかのか
EVと自動運転の融合が進む世界市場で、日本は完成車開発に固執し、EV部品自給率10%未満、国内就業人口減少など構造課題に直面する。部品、メンテナンス、知財を再設計し、社会実装単位で競争力を取り戻す戦略が急務である。
EV市場で価値再創出
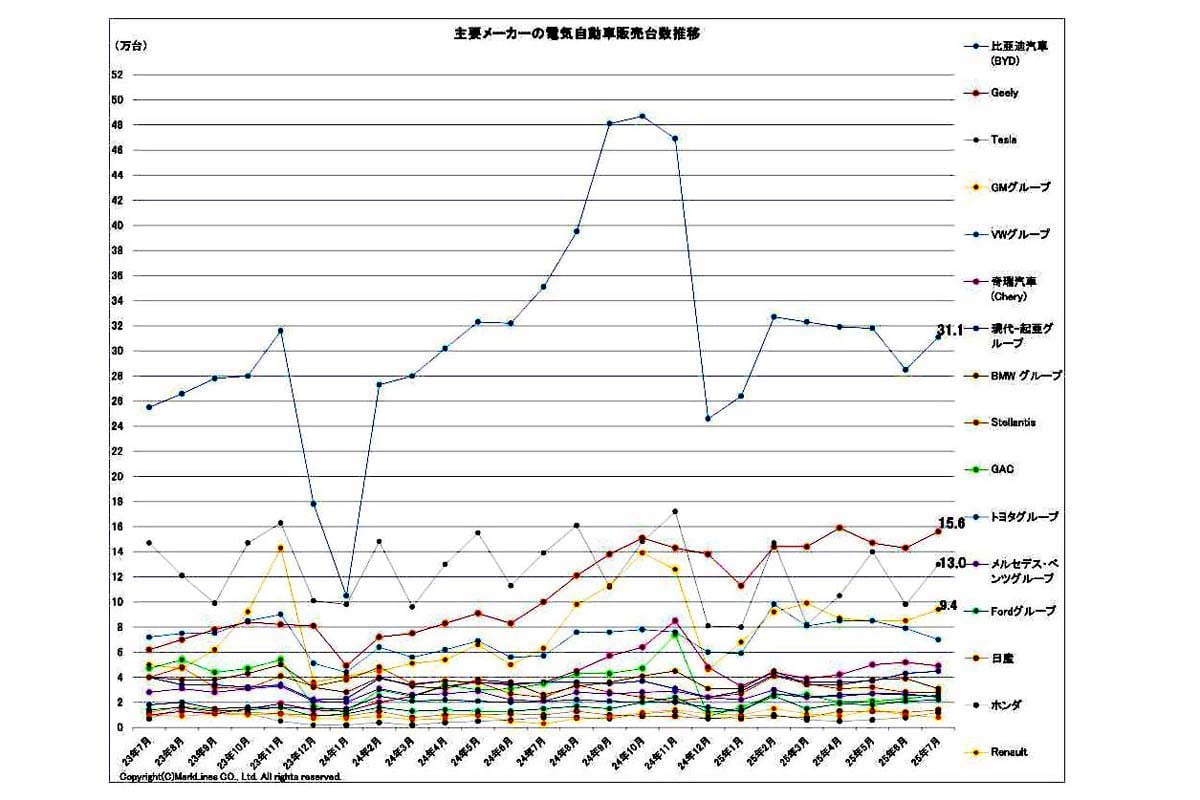
ふたつめの生き残りの道は「メンテナンスとリサイクルを軸にした産業モデル」、三つめは「海外人材と知財流通のハイブリッド化」である。
EVは内燃機関車に比べ、整備工数が約40%減る。そのため、整備業界は大きな変化の波に直面している。しかし同時に、EVの普及は使用済み電池やAI搭載センサーの再利用、解析、診断技術といった新市場を生み出す。
現在、日本国内で回収されるEVバッテリーの再資源化率は30%未満だが、リチウムやニッケルの回収技術を独自に高めれば、
「持続可能な再生型モビリティ国家」
としてのブランド化も可能である。従来型の整備視点を超え、EVを念頭にアフター市場ではなく「価値再創出産業」として制度設計を進めることが必要だ。メンテナンスとリサイクルの融合で勝負する姿勢が求められている。
国内の自動車関連就業人口は2010(平成22)年の約550万人から2024年には約470万人に減少した。技術者の平均年齢も45歳を超え、海外技術人材の受け入れが避けられない状況にある。一方、日本の特許ライセンス収支は2023年に2兆円の黒字を記録している。
中堅大学の工学部では堅実な技術者育成を目指す教育が進み、結果として優秀な技術者が生まれ、知財も豊富に蓄積されている。ゆえに、知識を製品化だけでなく輸出する方向で、
「知財を売れる人材」
を育成する社会戦略が不可欠である。海外技術者との協働開発や、世界の大学との研究連携を強化すれば、国内完成車メーカーが「知の輸出企業」となる可能性もあり、急速な変化にも対応できると考えられる。