「口だけ課長」「人気取りの部長」 上司を恨んでも“自己成長”には全く意味がない理由【連載】上司ガチャという虚構(3)
- キーワード :
- 組織, 上司ガチャという虚構
若手社員の3年以内離職率は約35%。企業は部下の信任が得られなければ上司を続けられない仕組みを導入し、権限型から信頼資本型への組織改革を進めている。心理的安全性と相互成長を軸に、企業文化そのものが変化しているのだ。
上司の「絶対性」崩壊
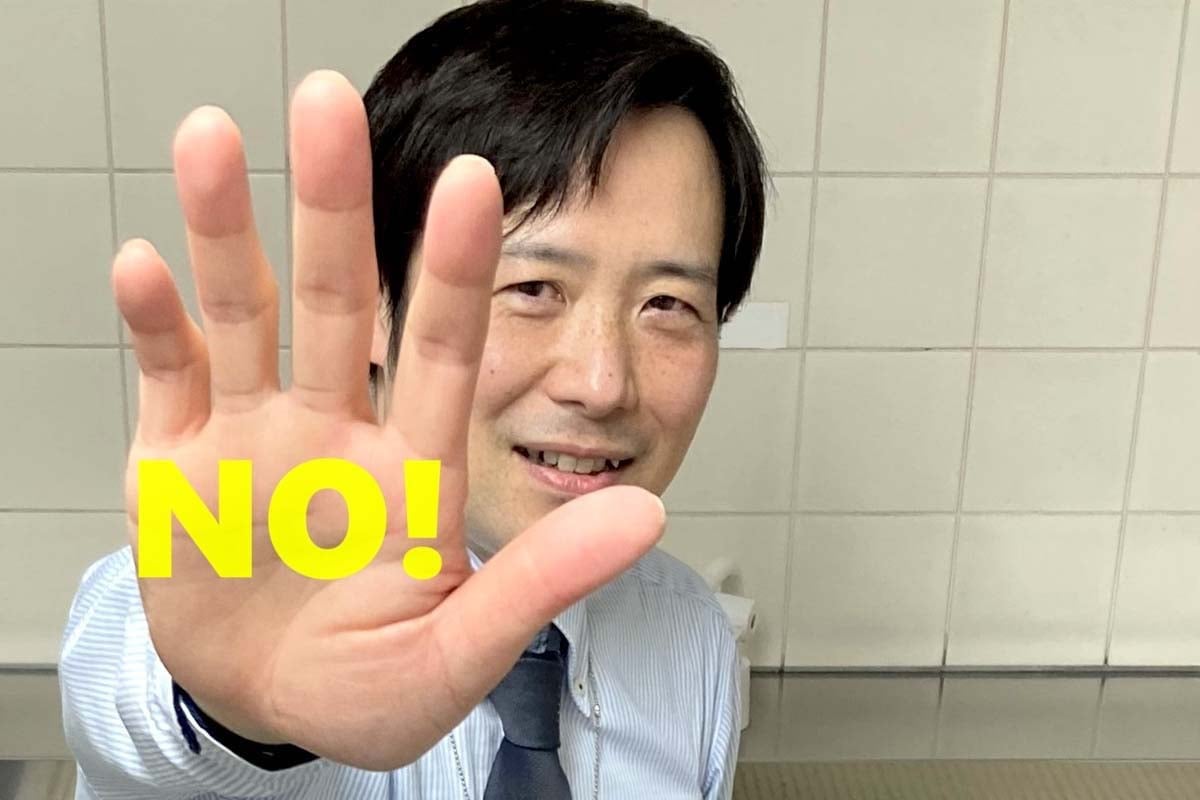
最近、若い世代の間でよく聞く「上司ガチャ」という言葉。どんな上司に当たるかは運任せで、自分では選べない――そんなもどかしさを端的に表している。しかし、そもそも上司を変える力はほとんどの人にない。だから「当たり・ハズレ」にこだわっても意味はなく、不満を運のせいにしていては自分の成長の機会を逃してしまう。本連載「上司ガチャという虚構」では、上司を「良い・悪い」で単純に裁くのではなく、無駄な労力に振り回されず、自分の成長や適応力に目を向ける視点を探る。変化の激しい職場で、自分の市場価値をどう磨き、キャリアをどう守るか。そのヒントを丁寧にひも解いていく。
※ ※ ※
かつて日本の会社員にとって、上司とは「天から降ってくる存在」、つまり会社が決める絶対的権力だった。どんなに理不尽でも黙って従うのが、組織人としての常識であった。しかし、この前提は根底から崩れつつある。
背景には若手社員の高い離職率がある。厚生労働省によれば、新卒入社3年以内の離職率は
「約35%」
に達する。人材の流動化が進み、従来の「若者に我慢を強いる」組織モデルはもはや成り立たない。企業は辞めさせないために必死である。正直にいえば、諦めにも似た現実的判断から、成長できる環境づくりに視点を切り替えざるを得なくなったのだ。