バスは消え、タクシーは来ない…全国2割「移動難民」化の悲劇! なぜ「足」は奪われたのか? 【連載】牧村和彦博士の移動×都市のDX最前線(28)
- キーワード :
- 鉄道, バス, 路線バス, 牧村和彦博士の移動×都市のDX最前線
日本全国で進行する交通空白問題。マイカーと公共交通の移動格差が広がる中、2024年4月からタクシーを含む新基準が導入された。地域の実情に応じた対応が求められる中、今後の交通サービスの改善には何が必要か、注目が集まる。
運転士不足が招く崩壊
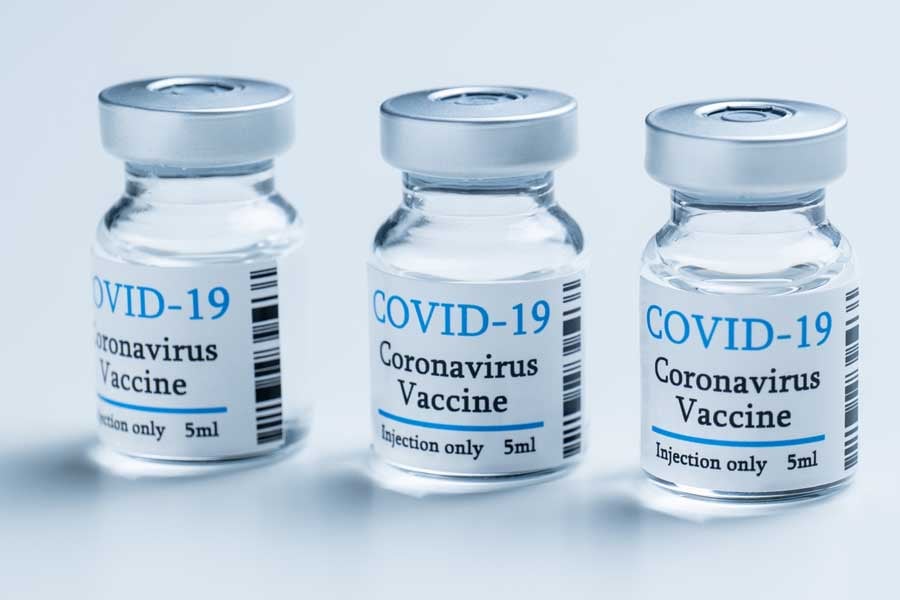
パンデミックのなかで公共交通の運転士の離職や転職が急増し、パンデミックを克服した後もさらなる路線バスの減便や撤退、タクシーの廃業が続いており、交通崩壊が止まる気配はない。
その要因のひとつに、筆者(牧村和彦、モビリティデザイナー)は日本独自の
「交通空白」
という考え方があると考えている。本来、地域の移動は交通サービスの程度が高いのか低いのかといった「程度」で測られるべきものであろう。残念ながら現場で運用されている交通空白地域はその多くが、
「空白かそうでないか」
「ゼロかいちか」
で色分け、峻別されてしまっているのが実情だ。
交通空白の基準が地域でまちまちである点も課題ではあるものの、行政としては、交通空白の存在自体が喫緊の政策課題となり、この交通空白をどのように埋めるかが、現政権の最優先課題だ。基準は行政の裁量で決めることができることから、行政によってはできるだけこの交通空白を小さく見せたいという思惑が生じる可能性もある。
一方で、交通事業者は交通空白地域を「新規参入の防波堤」と捉え、独自の防衛策が根付いてしまったと感じる。そして今、各地で生じているコミュニティバス撤退問題に象徴されるように、運転士不足によりこの防波堤は、徐々に全国で決壊しつつある。