日本車はなぜ売れ続けるのか? なぜ強いのか? 厳しい自然環境が育んだ耐久性と信頼性、円安の“追い風”で再考する
北海道で鍛える信頼性
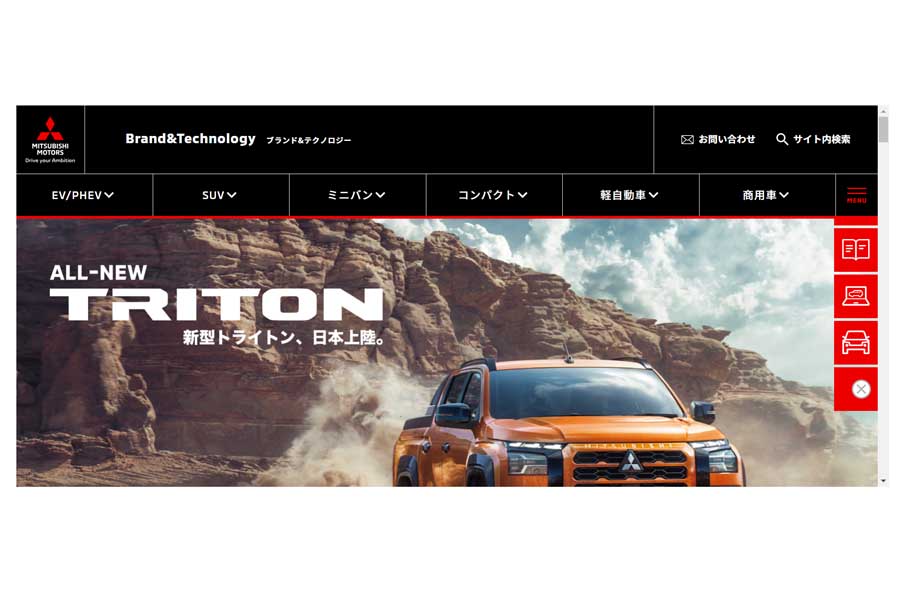
実は、この成果を支えている要因のひとつに、日本の自然環境や気候の厳しさがある。
まず、日本の主要メーカーは、冬のテストを繰り返すことを前提に、北海道にテストコースを持っている。道北部の中央に位置するトヨタの士別テストコース(士別市)がその代表例だ。(ちなみに、メーカーはプルービンググラウンドと呼ぶことが多いが、本稿ではテストコースと呼ぶことにする)。
同地の冬はマイナス30度、夏は30度を超えることもある。つまり、気温差は60度にも達するのだ。そんな気候の厳しさもあってか、士別にはトヨタ系のヤマハ発動機やダイハツのほか、ブリヂストンも日本最大級といわれる冬用タイヤのテストコースを所有している。
このほか、十勝管内には三菱と日産自動車、上川管内にはホンダ、マツダ、スズキがテストコースを持っている。メーカーによっては冬しかテストコースを使用しないところもあり、60度の気温差をフルに体感することはできない。しかし、日本のほぼすべての自動車メーカーがマイナス30度の自然環境を必須と考えているのは心強い。
そして、北海道とは正反対の高温多湿の環境も重要だ。この点、海外だけでなく、国内でも沖縄などの離島を含め、さまざまな場所でテストや実戦が繰り返されている。また、海に近い地域も多く、塩害に長期間耐える必要がある。
自然環境とは別に、海外メーカーも日本のマーケットの厳しさや特殊性を重要視しているようだ。例えば、BMWが10年前のあるインタビューで日本をどう見ているかという記事があった。要約すると、次の2点が紹介されていた。
・日本には目の肥えた消費者が多い。そのため、BMWは日本を、消費者が新技術にどう反応するかを試せるマーケットと見ている。
・日本には国内メーカーの競争を勝ち抜いてきた優秀なサプライヤーが多いので、最新の技術動向の把握にも力を入れている。
結果、BMWが日本を重要なマーケットとみなしている証しのひとつが、いち早く日本に新型車を投入したことだ。右ハンドル対応からハイブリッド車のローンチまで、日本が優先されていると記事は結んでいる。