「テロとの戦い」時代における兵站の行方とは? 近代以前の戦略回帰か、融解する最前線・後方地域の境界線
「テロとの戦い」とロジスティクス
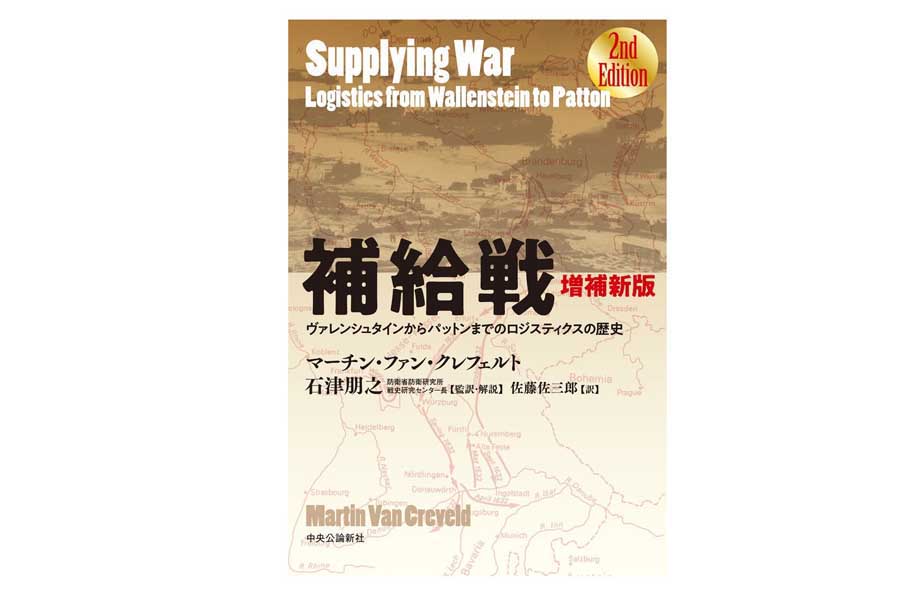
国家の正規軍同士の戦争を前提とした従来のロジスティクスのあり方は、今日、その有用性を徐々に失いつつあるように思われる。併せて、自己完結を旨とする従来のロジスティクスのあり方も、大きな見直しを迫られている。これまでは、自己完結こそが軍隊を他の組織と分ける大きな特徴であった。
テロやゲリラとの戦いに象徴される「新しい戦争」の時代には、その時代の要請に応じた、新たなロジスティクス・システムの構築が求められるが、これはむしろ、近代以前の軍隊のロジスティクスのあり方への「回帰」なのかもしれない。
この回帰について詳しくは、イスラエルの歴史家マーチン・ファン・クレフェルトの主著『増補新版 補給戦――ヴァレンシュタインからパットンまでのロジスティクスの歴史』(中央公論新社、2022年)を参照してもらいたい。社会の様相の変化と戦争の様相の変化の、強い関連性を理解できるはずである。
将来の戦争あるいは紛争は、ジャストインタイムでは対応できない可能性がある。例えば、周囲を敵対勢力――必ずしも軍隊である必要はない――に囲まれた基地および部隊に対するロジスティクスは、今日の軍隊が追求している高速かつ機動的な戦いでの効率的なあり方とは全く異なる条件下のものとなろう。
敵の組織的な戦闘力の破壊を目的とする従来の国家間の正規戦争――通常戦争――と異なり、ゲリラ攻撃やテロ攻撃――非通常戦争――を受ける状況下での固定的な基地あるいは部隊に対するロジスティクスは、従来のやり方とは大きく異なる、むしろ以前に行われていた「アイアン・マウンテン」――事前の膨大な物資の集積――を構築する方策へと「回帰」する可能性すらある。
事前対応型ロジスティクス態勢への移行
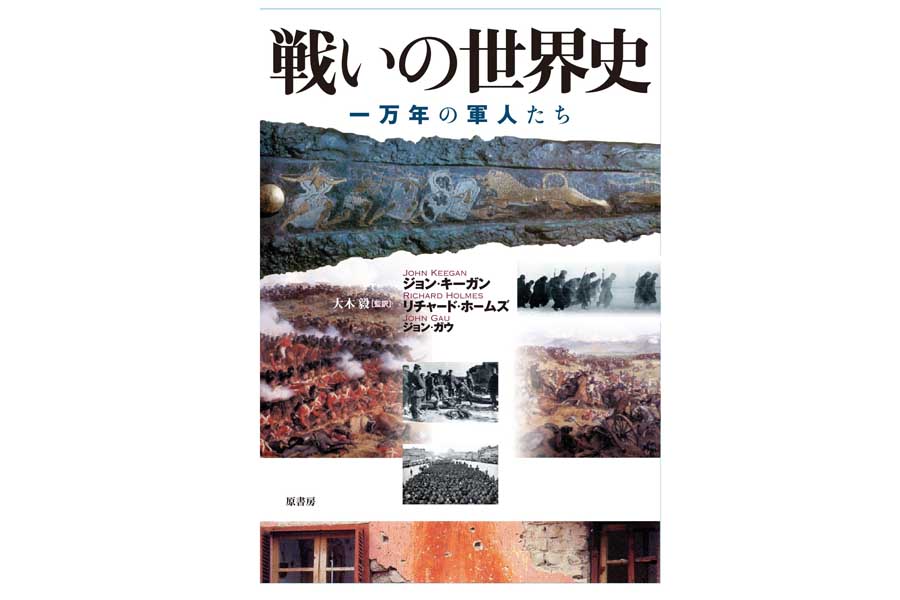
つまり、従来、自己完結を旨とした主権国家の軍隊が、今日の国家の枠組みを超えた紛争や活動――例えば非通常戦争(非対称戦争)や国連平和維持活動(PKO)――にいかに対応できるか、また、ロジスティクス業務の多くを民間企業に委託せざるを得ない今日の社会状況に軍隊がいかに対応できるかが問われている。
さらには、伝統的な事態対応型のロジスティクス態勢から、
「事前対応型のもの」
への移行も求められるであろう。テロやゲリラに象徴される非通常戦争が多発する今日、最前線と後方地域の境界(線)はますます曖昧になってきており、ときとしてこうした区分は無意味ですらある。
ある軍人の言葉を借りれば、ロジスティクスは決して「魅惑的(グラマラス)」な領域ではない。だが、戦争の勝利のためには必要不可欠な領域である。なぜなら、
「戦いに勝つための術(アート)である戦術とは、実際のところ、兵站上可能なことを成す術(アート)なのである」(ジョン・キーガン、リチャード・ホームズ、ジョン・ガウ共著『戦いの世界史――一万年の軍人たち』原書房、2014年)
からである。