「テロとの戦い」時代における兵站の行方とは? 近代以前の戦略回帰か、融解する最前線・後方地域の境界線
最前線への権限委譲

近年、軍事の領域では突発的なテロやゲリラ攻撃などに迅速に対応できるよう、現場あるいは最前線の部隊への権限委譲――民間では「アダプティブ」として知られる――の必要性が改めて認識されており、軍事ロジスティクスの領域も例外ではない。
歴史上、最前線への権限委譲に関しては「任務戦術」、ドイツ語で「Auftragstaktik」と呼ばれる方策が存在する。今日では、英語で
「mission tactics」
「directive command」
「mission command」
などとも表現されるが、近現代においてその発端は、泥沼の塹壕(ざんごう)戦に陥っていた第1次世界大戦末期、ドイツ陸軍が考案したとされるものである。興味深いことに今日これが、それもロジスティクスの領域との関連で改めて注目されているのである。
周知のように、第1次世界大戦末期のドイツ陸軍は、敵の最前線をひそかに突破して敵陣の内部深くに侵攻し、小規模な部隊での分散行動によって敵を背後や側面から攻撃してかく乱する「浸透戦術」と呼ばれる方策を用いた。
そして、この浸透戦術を可能にするために権限を下位の部隊に委譲したのである。上級指揮官は目標と大まかな方針だけを示すにとどめ、任務を遂行する具体的方法は最前線の下級指揮官の判断に任せた。
実は、当時は敵陣に侵攻した部隊は、技術の未発達などの理由から本隊との連絡が途絶えてしまうため、権限を委譲しなければ行動できなかったのである。
米軍が権限委譲を進める理由
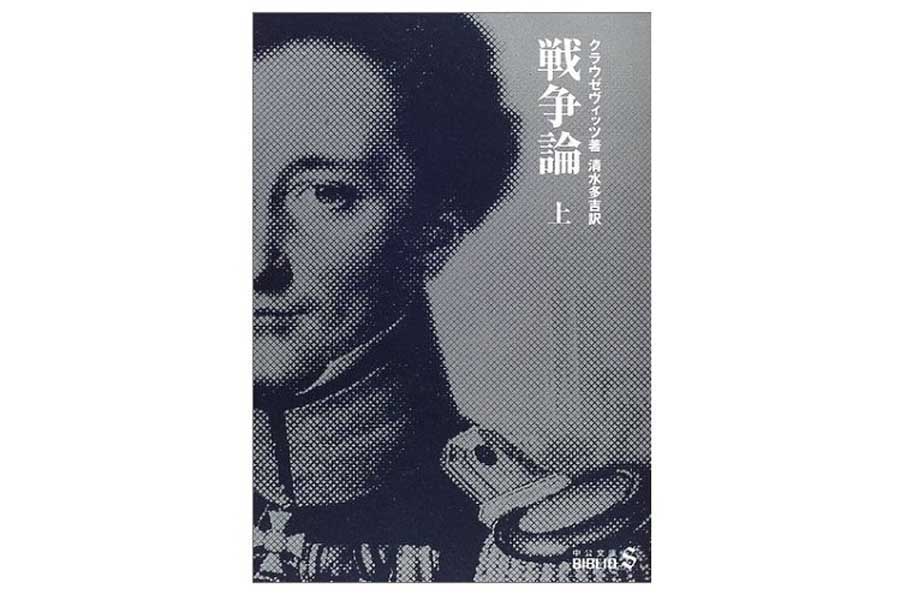
なるほど今日の軍隊は主としてICT(情報通信技術)の発展の結果、最前線の状況がリアルタイムで本国の中央で把握できるようになった。
それにもかかわらず、米軍は任務戦術の概念を一部に採り入れて最前線への権限委譲を進めているが、その狙いのひとつはもちろんテロ対策である。戦闘が始まって、その度に上級司令部に指示を求めていたら、対応が後手に回ってしまうからである。
同時に、中央から最前線の状況がリアルタイムに見えるようになった結果、逆に
「現場の判断を尊重する必要性」
が改めて認識されたともいえる。
かつてプロイセン=ドイツの戦略思想家カール・フォン・クラウゼヴィッツは『戦争論』のなかで、机上の計画と現実の戦いとの違いを「摩擦」という概念を用いて説明した。
確かに、気象条件や兵士の疲労度など、事前に予測することのできない要因が戦争の勝敗には大きく影響する。それらを概念化したものが「摩擦」であり、クラウゼヴィッツは
「戦争は摩擦に満ちている」
と述べたが、この事実は今日でも変わらない。
だからこそ、最前線に権限を委譲し、その意向を尊重する必要性が認められたのであるが、この事実は戦いの骨幹であるロジスティクスにも当てはまる。