「EVが増えるほど税が消えていく……」 消失する約145兆円の代償――脱炭素の裏で低所得国が直面する“財政的自滅”へのカウントダウン
走行距離課税という選択肢
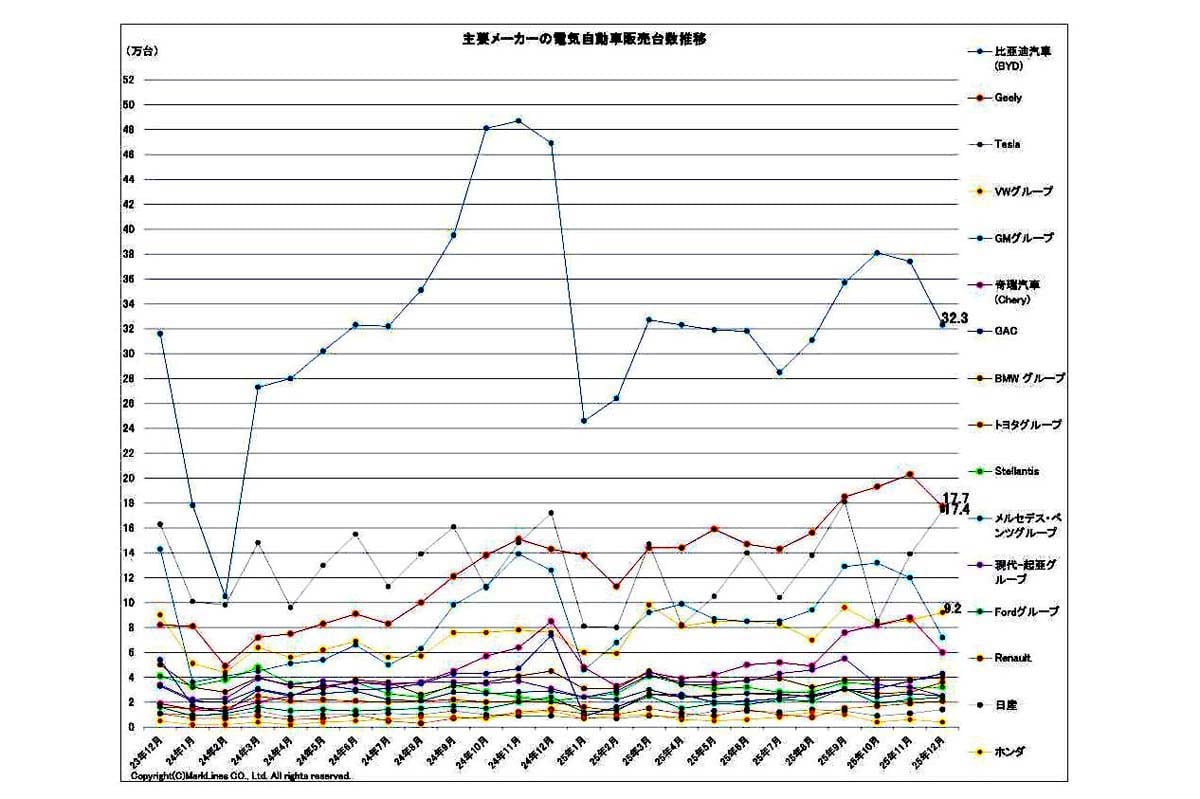
燃料税の収入が大きく落ち込んだ場合、道路の維持費をどう確保するのか。この問いは欧米でも差し迫った課題になっている。EVへの移行は、長く支えとして機能してきた公共財政の枠組みに揺さぶりをかけている。
何十年もの間、道路網の維持管理はガソリンやディーゼルに課される税に頼ってきた。走れば走るほど燃料を使い、その結果としてインフラに資金が回る。こうした関係がEVの全面的な普及によって成り立たなくなる。
この変化の中で、走行データを握るメーカーが、実質的に徴税を支える役割を担う立場へ近づいていく可能性がある。公的権限と企業側の影響力の関係が、これまでとは異なる形に移っていく余地は小さくない。
現実的な対応策として、EVに対する走行距離に基づく課税が取り沙汰されている。フランスを含む欧州各国でも議論は活発だ。車両に通信機能を備え、登録された自動車ごとの走行距離を把握すること自体は技術的には難しくないように映る。ただそれは個人の移動の軌跡が常時把握される状況への入口でもあり、運転者の抵抗感を高めるおそれがある。
課税が走行履歴という変動する情報に結び付くことで、車の価値は行政の判断次第で左右されやすくなる。結果として個人が所有するよりも、税負担を調整しやすい法人が管理する形へ移行する動きを後押しする可能性もある。
走行データをどのように扱い、守るのかは、なお解かれていない問題だ。プライバシーの確保や行動の把握につながる点への懸念は主要な論点として残る。また課税の水準や方法を誤れば、車両価格が高めなEVの経済的な魅力を削ぎ、購入意欲を弱めかねない。それでも走行距離課税を巡る議論は、賛否を超えて導入の時期や受け入れられ方、対象の広げ方といった具体論に入りつつあるように見える。
実現は時間の問題なのか。移動という行為の価値の測り方が変わりつつある中で、この論争が続くことだけは確かだろう。