「鉄道軽視」「利益偏重」──JR東日本36事業本部制に批判コメントが殺到した根本理由
2026年7月、JR東日本は全国支社制を廃止し36事業本部へ再編する。非鉄道収益比率6割を目指す一方、現場軽視や安全不安の声も根強く、利用者・地域との信頼維持が改革成功のカギとなる。
現場信頼失墜の懸念
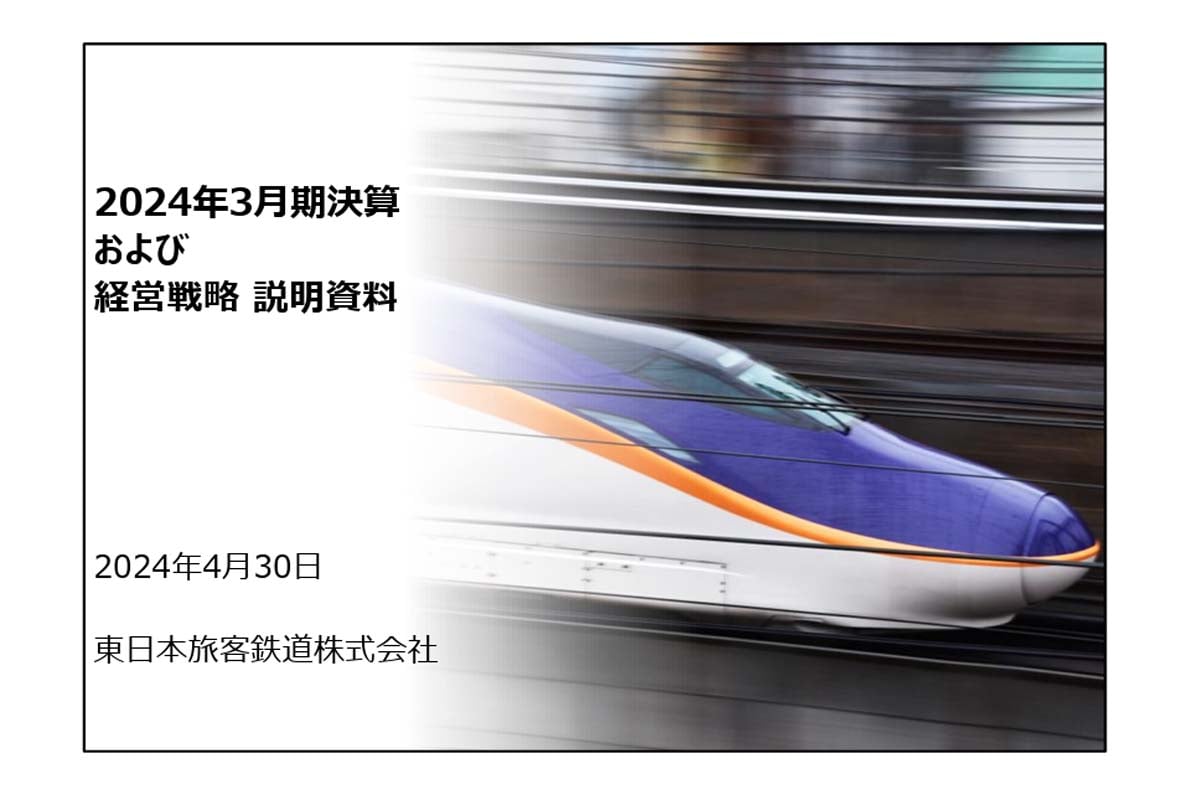
今回の36事業本部制に対するインターネット上の批判には共通点がある。
・JR東日本は市場利益しか見ていない
・本業の鉄道事業が軽視されるのではないか
という指摘だ。新聞報道によれば、JR東日本は2027年度を目途に、非鉄道部門の営業利益を全体の6割程度に拡大することを目指している。なかでも不動産事業を安定的収益源として重視する。営業利益率は、2023年度の鉄道事業が3.6%、不動産事業が10.4%、ホテル・商業施設が12.7%となっている。新型コロナ禍によるテレワークの普及などで定期券収入は戻りにくく、鉄道事業単独での収益拡大は見込みにくい。
2024年4月に公表された経営戦略資料を見ると、モビリティ事業は限定的で、
・地域開発事業
・生活ソリューション事業
への投資案件が多いことがわかる。駅ナカや沿線商業施設、沿線開発への資本配分を増やす方向は既定路線である。JR東日本はすでに
「交通の拠点から暮らしのプラットフォームへ」
と提供価値を転換している。単なる鉄道事業者ではないと公言するなかで、非鉄道事業の収益拡大戦略と現場の
・人員削減
・サービス低下
への潜在的批判が並存する。36事業本部制はその両立を狙う側面もあるが、現場負担は見過ごせない。千葉地区の「朝運転・昼販売」の兼務例のように、働き方改革が本当に進むのか疑問は残る。
さらに、人手不足下での賃金再配分が現場の理解を得られるかも課題だ。人材流出による人材難のリスクもある。現場の声を集めれば、トップ層の現業経験の少なさや理解不足への不信感も根強い。不動産やSuica関連事業で収益構造は変化したが、体制改革によって現場との信頼関係が毀損されれば、本業での信用にも長期的な影響が出る可能性がある。