「鉄道軽視」「利益偏重」──JR東日本36事業本部制に批判コメントが殺到した根本理由
36事業本部の課題
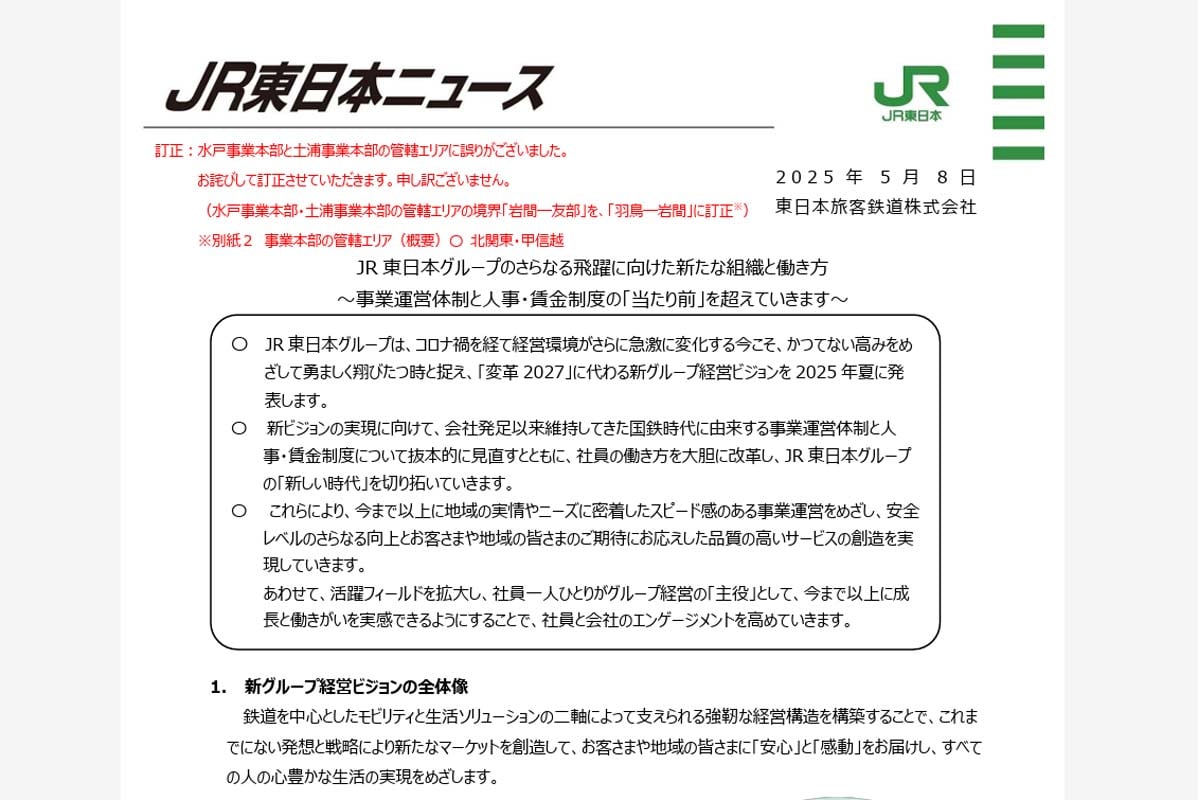
JR東日本は、現行の12支社体制から36の事業本部へ移行する。では、何が変わるのか。公式リリースを見ると、新旧体制の違いは明確だ。
現行の組織は
・第一線の職場
・本部・支社
・本社
の3層構造である。新体制では
・第一線の職場と本部・支社を融合した事業本部
・本社
の2層構造に変わる。36の事業本部はそれぞれ、管轄エリアの経営の基本単位となり、地域との接点になる。
本社機能も「グループ戦略部門」と「事業執行部門」に分化する。各事業本部は地域の実情に応じた輸送サービスの展開や、地域との共創役を担うことになる。
利用者目線では、各事業本部の所管路線、人口カバー、輸送密度、営業距離の再分配に不安がある。ネット上では
・路線またぎ問題(例:上野東京ラインや湘南新宿ラインのように、複数の路線をまたいで頻繁に運行される列車群)
・境界の混乱(結局、国鉄時代から運行されていた越境列車が減り、事業本部の分岐駅での乗り換えが増えるのではないか、という懸念など)
に関する懸念が挙がっている。
自治体との関係も課題だ。過去には、自治体が負担増でも路線存続を求めることがあった。しかし、事業本部単位では「JR東日本が黒字で補填すべき」との意見が目立ち、合意形成が難しくなる地域が増える可能性もある。
事業本部単位のトラブル対応も不透明だ。ある事業本部の判断が全線に影響することもあり得る。組織マネジメント論の観点から考えれば、縦割り組織は
「セクショナリズム(部門・部署・地域などの部分的な利益や考え方を優先し、全体の調和や目標を軽視すること)」
を生みやすい。小さな組織のローカルルールや個別運営が、組織全体の活性化を妨げることもある。
36事業本部における横断的な機能、いわゆる「串刺し機能」が重要になる。縦割りを進めるなら、リスクを解消する横の機能を組み込む必要がある。大学業界で導入されている「学環」のようなシステムが参考になる。学環は学科を横断して学べる仕組みで、特定の課題解決に向けた実践的教育を可能にする。
JR東日本の場合も、組織図を変えただけでは輸送網の断絶や連携摩擦が減る保証はない。リスク低減のための横串型機能の設置が不可欠である。