ホンダ・日産「ソフト共通化」が直面する三つの壁――SDV時代に問われる“自社OS”の存在意義とは何か?
自動車業界はSDVへの大転換期にある。ホンダと日産は、2020年代後半に向けて次世代車両のソフトウェア基盤を共通化する計画を進めている。だが、独自OSの開発や投資負担の違い、設計思想の非対称性が統合を難航させている。両社は収益性改善と開発効率化の両立を模索しつつ、設計自由度と長期的柔軟性のバランスをどう取るかが経営課題となっている。
技術統合に潜むリスク
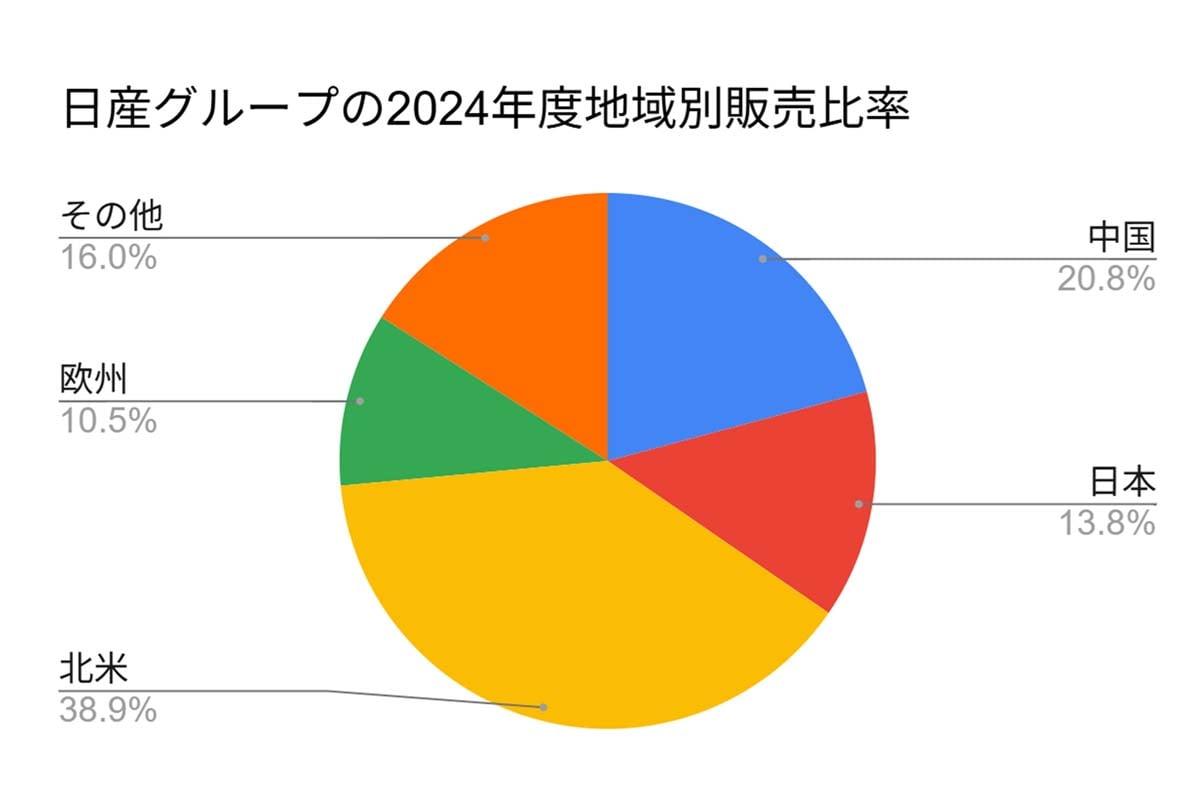
ホンダと日産のソフトウェア基盤共通化には三つの懸念がある。
まず、「戦略の非対称性」だ。ホンダは既に独自の思想と技術資産を持つ。日産と歩調を合わせるには調整コストがかかる。一方、日産が主導するには十分な資産が現時点で見えない。
次に、「共通設計の効率性」が課題となる。両社の思想や開発フェーズの違いが、非効率や遅延を招く可能性がある。特にホンダはすでにOS開発を進めており、調整にともなうリスクが大きい。
最後に、「投資回収の不透明化」が懸念される。ホンダの長期投資を象徴するASIMO OSや0シリーズが、共通化によって相対化・希薄化する恐れがある。これは十年単位の先行投資の根幹を揺るがしかねない問題だ。
経営的には共通化は妥当な選択に見える。しかし、開発現場では誇りと責任がかかった技術資産の共有となり、心理的負担は大きい。ソフトウェアは完成で終わるものではなく、リリース後も改善を続ける生きた存在だ。
日産にとって共通化は戦略的パートナーとしての意義が大きい。だがホンダは、自社の軸足を維持できるかどうかが問われる。両社の意志と技術をどうまとめるか、経営の舵取りは一層難しくなるだろう。