世界4位へ躍進 今治造船×JMU統合で挑む「日本造船」復権──高付加価値と脱炭素で中韓を逆転できるか?
- キーワード :
- 船, 今治造船, ジャパンマリンユナイテッド
中国・韓国に押されてきた日本造船業が、今治造船によるJMU子会社化で再起を図る。年間建造量は500万総トン超、国内シェアは5割に達し、世界4位の規模へ。高品質・高効率を武器に、再びグローバル競争の舞台に挑む――再編の先に問われるのは、持続可能な成長モデルの実現だ。
世界4位への再浮上
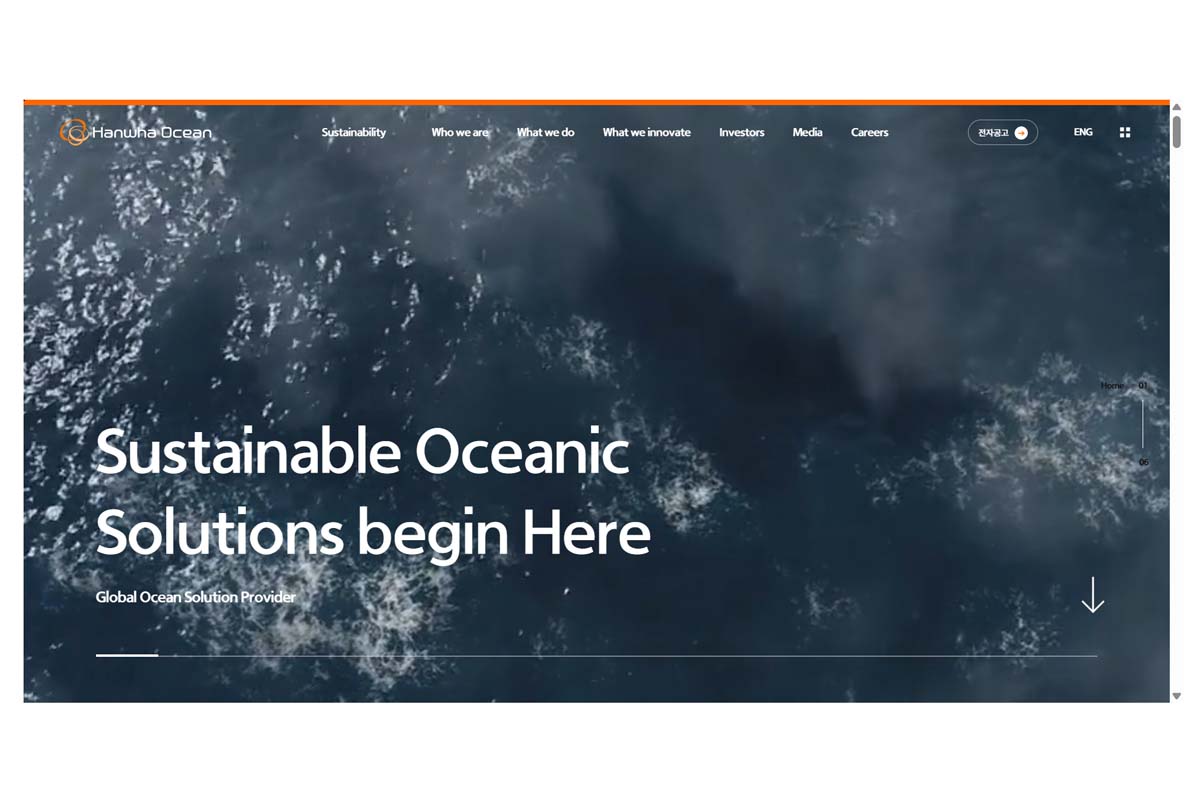
この統合により、今治造船グループの国内竣工量シェアは5割を超える規模となる。続いて
・大島造船所
・名村造船所
・新来島どっく
がそれぞれ10%前後のシェアを占めており、今治造船グループの圧倒的な影響力が明らかだ。
世界市場に目を向けると、両社の年間建造量合計は約500万総トンに達すると予想される。これはハンファオーシャンを上回り、
「世界4位」
の建造能力となる。さらに、韓国の現代重工業やサムスン重工業に匹敵する競争力を持つことになる。かつて世界シェアの半数以上を占めていた日本造船業が、再び
「世界のトップグループに返り咲く可能性」
が高い。この動きは業界に大きな影響を与えると予想される。まず国内では競争環境が激変し、寡占化が加速するだろう。従来、複数の造船所が受注を巡って競争してきたが、統合により今治造船グループが国内建造量の約半分を占めることで、実質的な寡占状態が形成される。これにより中堅・中小の造船所は、
・ニッチ分野への特化
・今治造船グループとの連携強化
を模索する必要に迫られる。国内競争の縮小は業界効率化を促す一方で、多様なプレイヤーの育成を難しくする可能性もある。
また、国際的には中国・韓国の巨大造船グループとの直接対決が避けられない。特に高付加価値船や特殊専門船種の分野で、これまで以上に激しい受注競争が繰り広げられるだろう。日本造船業の今後は、この競争の中で技術力と効率性をどう磨くかにかかっている。