日本の自動車メーカーは今すぐ「バッテリーEV」にかじを切るべきだ! 業績絶好調&HVシフトの時こそチャンスである
日本の自動車メーカーが好調とはいえ、東京オートサロン2024の状況を見ると、BEVはまだラインアップの主力ではなく、開発途上であることがわかる。
BEVの進化と「生活の変化」
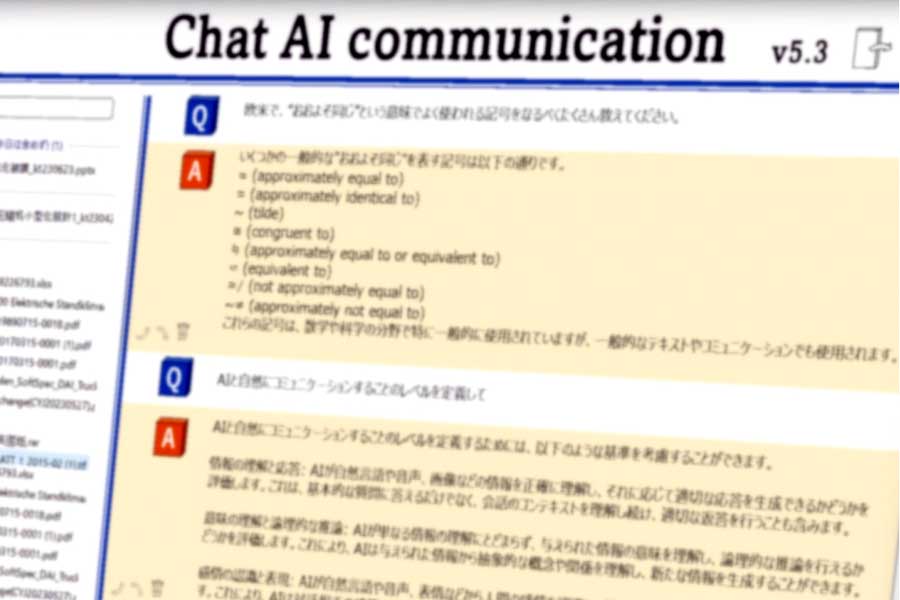
また、生成AIの普及は音声認識を飛躍的に向上させると期待されている。とすれば、近い将来、運転中の多くの操作において、安全性の観点から音声が主要な操作手段になることは容易に想定できる。
次世代の音声認識については、2023年、メルセデスベンツのインフォテインメントシステム「MBUX」が、すでに米国でチャットGPTを使ったテストを行っている。また、新しいもの好きの若いBEVユーザーには、この音声コマンド機能は喜ばれそうだ。特にテスラについては、日本でも試乗体験などの書き込みがネット上に多く見られる。
つまり、彼らはBEVによる運転シーンの変化だけでなく、「生活の変化」も楽しんでいるのかもしれない。なぜなら、BEVはスマートフォンのようなスマートデバイスになり得る可能性もあり、何よりもそれらとの親和性が求められるのだ。
そもそもクルマの購入は、何らかの「生活の変化」を望むことがきっかけとなる。多くの都市部では、単純な移動手段としては公共交通機関で事足りる。
もちろん、地方ではクルマが必需品であることも多いが、実用車ばかりが売れるわけではない。したがって、ここで購入されるクルマの一定数は、「生活の変化」への欲求とも結びついているわけだ。
その意味で、BEVが「生活の変化」をもたらす能力は、従来のエンジン車やHVよりも高いことは間違いない。BEVを前提にすれば、消費電力の高いハイスペックPCを、走行中はもちろん駐車中も含めて、いつでもどこでも高性能なスマートデバイスとして機能させることが可能になるからだ。