4年で108人死亡 岡山県「人食い用水路」はなぜそのままにされているのか? 少なくない“柵”反対の声、驚きの理由とは
岡山県岡山市や倉敷市には、危険な用水路が当たり前に存在している。当然、転落事故は多い。いったいなぜこんなに多いのか。ネットで話題になった、敦賀市の側溝トラブルを契機に振り返る。
近年まで問題化されなかったワケ
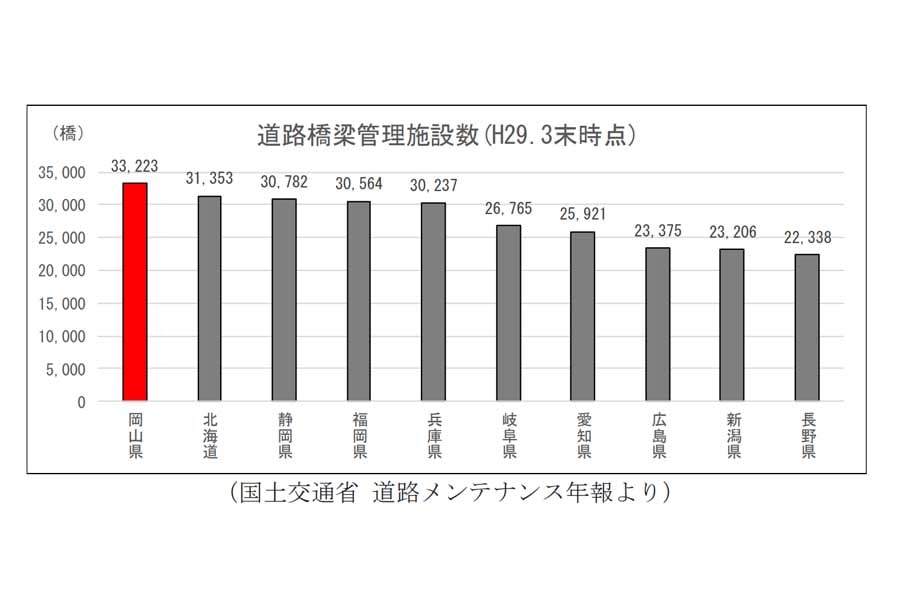
道路港湾管理課の担当者は、丁寧に解説してくれた。もともと干拓地である岡山市南部や倉敷市には縦横無尽に用水路が走っている。その総延長は岡山市内で約4000km。倉敷市内で約2100kmにも及ぶ。
そもそも用水路がとても多いのだから、それに比例して転落する人が多いのはわかる。その上で担当者は、事故が目立つようになった背景として、次のふたつを挙げる。
・干拓地の田畑が宅地化され人口が増えたこと
・高齢化が進み転落し、かつ重症となる人が増えたこと
「以前は、用水路に落ちた程度なら自分ではいあがっている人が多かったんです。しかし、高齢者が増加したことで、転落した際に救急車を呼ばなくてはならないようなけがを負ってしまう人が増えているのだと思います」
さらに担当者と話しているなかで、岡山出身の筆者は、近年まで問題化されなかった背景に岡山人の“気質”があると感じた。どういうことかといえば「用水路に落ちた」と人に知られるのは
「ふうがわるい(みっともない)」
のである。
ほかの地域では心配されそうだが、岡山では「あの人は用水路に落ちたんで」と、少なくとも1か月は笑い者にされる可能性は高い。親戚であれば法事で顔を会わす度にいわれそうだ。
だから、岡山では用水路に落ちても多少のけがなら自力ではいあがって、救急車を呼ぶこともなかった。ところが、近年は高齢者の転落が増えたため多少のけがではすまず、救急車を呼ぶことも増えた。このことで問題が可視化され、岡山人も笑い者にしている場合ではないとようやく気づいたわけだ。