SNSで暴言を繰り返す「鉄道オタク」が、人間より「bot」に近い根本理由
- キーワード :
- 鉄道
繰り返す者、繰り返させられる者

SNS上で鉄道に関する議論を目にすると、しばしば暴言が飛び交う光景に遭遇する。
「にわかは黙れ」
「知識もないくせに語るな」
「間違った情報を流すな」
といったような言葉が、感情を帯びた鋭利な刃物のように繰り出される。「にわか」とは、何かに対して新しく興味を持ち始めた人や、まだ深く知識を持っていない人のことだ。
これらの言葉を発する者たちは、あたかも自らの意思で発言しているように見える。だが、その実態を注意深く観察すると、彼らは本当に
「自らの意思で語っている」
のだろうか――という疑問が湧いてくる。鉄道への愛が深いからこそ、知識の誤りに敏感になる、そう考えれば、一見、彼らの態度は筋が通っているように思える。しかし、彼らの発言にはある特徴がある。どれも
・同じようなパターンで
・同じようなタイミングで
繰り返されるのだ。まるで決まった条件が揃えば、決まった言葉が自動的に吐き出される「bot」のようだ。
不安を生む言葉の力と社会的影響
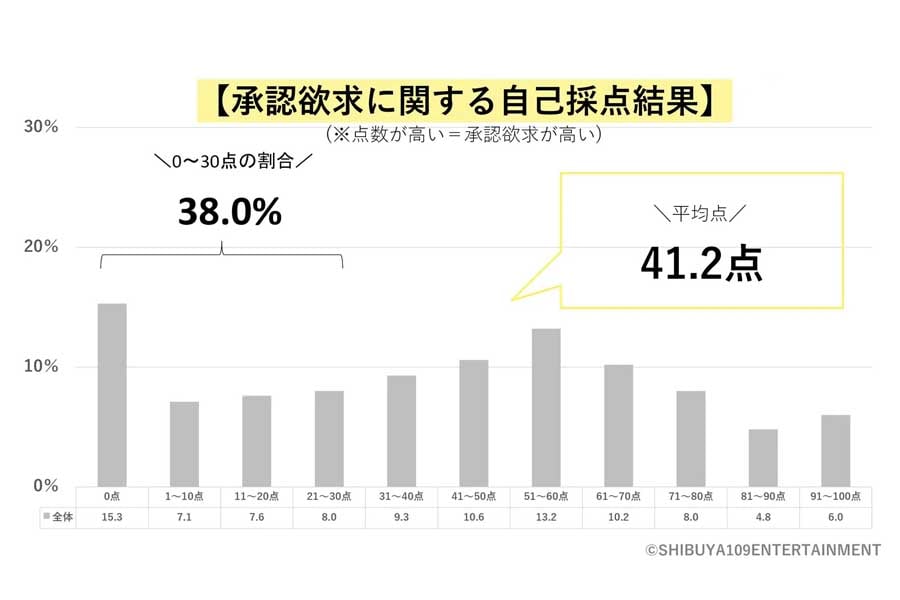
この現象を説明するには、元東京都立大学教授で社会学者の宮台真司氏が提唱した「言葉の自動機械」という概念が役立つ。「言葉の自動機械」とは、次のようなものだ。
「自分が発話の主体だと思いながら、神経症的な不安ゆえに社会的に構築された決まり文句をボットのように吐き散らす、言外・法外・損得外の豊かさを知らないカワイソーな存在」(2022年4月9日付ツイッター)
自分が話していると思っていても、実は社会的に決まった言葉を無意識に発して、不安を解消しているという意味だ。つまり、言葉を意識せずに反射的に繰り返す行動である。この場合の「神経症」とは、直接的に不安を解決するのではなく、無関係な行動を繰り返して不安をまぎらわせることを指す。たとえば、潔癖症の人が手を何度も洗うのは、手が汚れているからではなく、不安を解消するためだ。根本的な問題解決にはなっていない。
SNSで暴言を繰り返す一部の鉄道オタクは、鉄道文化を守るため、知識を広めるために話していると思っている。しかし、実際にはその言葉が自らの
「内面の不安や恐れ」
から来ていることがある。つまり、知識を話すことで自分の価値を証明し、不安を解消しようとしているのだ。発言の目的は伝えることではなく、ただ「吐き出さずにはいられない」という衝動から来ている。
こうした発言がSNSで繰り返されると、それが「文化」として広がり、他人の意見に批判的に反応することで、自己の存在意義を確認しようとすることがある。言い換えれば、他人を「にわか」として排除することで、自分の立場を強化し、安心感を得ているのだ。
このような言動は、社会的な役割や立場に不安を抱える人にとって、安全な場所を提供する。自分の知識や経験を他者に正当化し、周囲との差を強調することで、不安や劣等感を和らげようとしているのだ。言葉の背後には、単なる知識の差や認識の違いだけでなく、深い心理的メカニズムが隠れている。