山手線の北側部分が、まるで「M」みたいな形になってるワケ
- キーワード :
- 鉄道
池袋駅誕生の経緯解剖
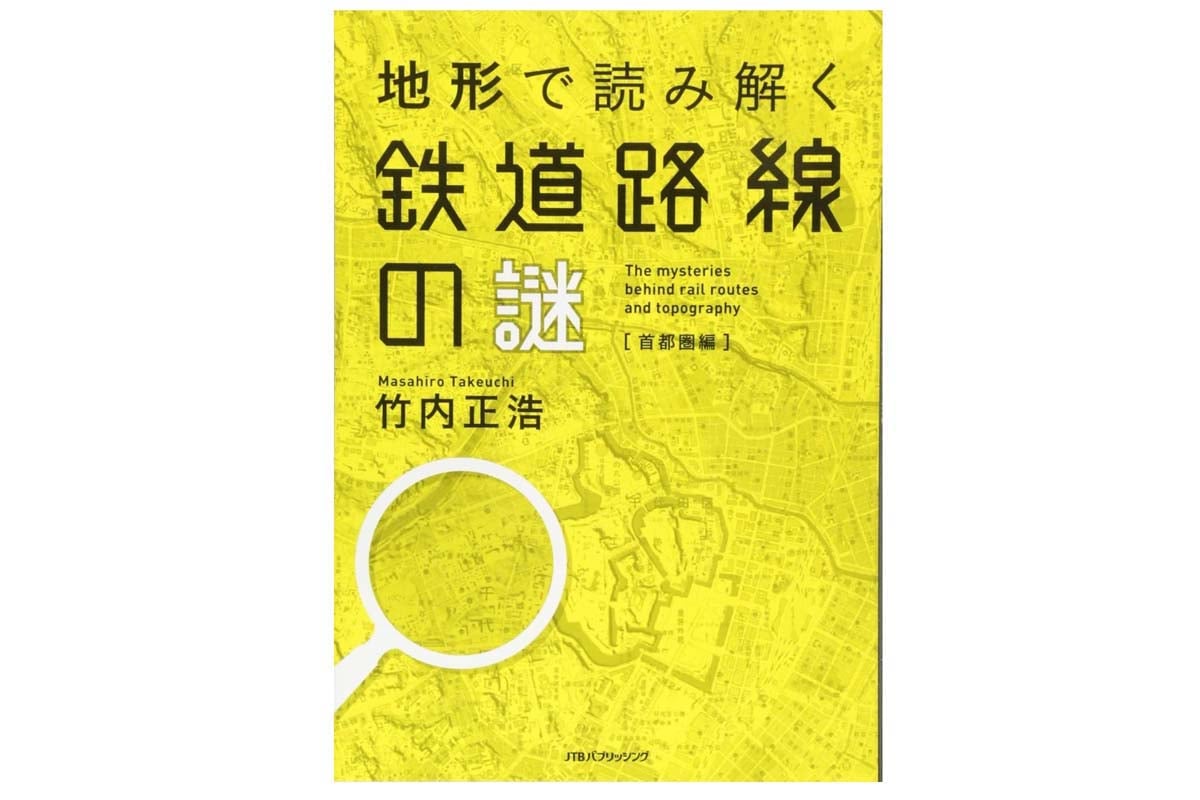
資料を探したところ、山手線に関する疑問を解き明かす研究書に出会った。紀行エッセイストの竹内正浩氏による『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』(JTBパブリッシング、2015年)である。
驚いたのは、もともと池袋には駅を設置する予定がなかったことだ。当時の豊島地域は人口も少なく、都市的な中心性がまだ形成されていなかった。駅設置は当初、計画の外にあったのである。しかし都市計画者や鉄道会社は、周囲の地形、既存路線との接続、将来の人口増や都市発展の潜在性を考慮し、戦略的に判断した。丘陵や谷戸の地形条件も無視できず、短絡的なルート選択ではなく、都市成長を見越した立地が優先された。
現在の埼京線は1885(明治18)年に日本鉄道品川線として品川~赤羽間で開通。その後、上野~熊谷間は1883年に開業済みで、1896年には田端駅が開業する。田端方面から赤羽駅を経由せず、南側でショートカットする路線が計画され、豊島線という仮称で建設が進められた。このルート選択は地理的短絡ではなく、都市発展の潜在力を重視した戦略的判断であった。
時系列で整理すると次のとおりである。
・1883年:日本鉄道上野~熊谷間が開業
・1885年:品川~赤羽間(品川線)が開通
・1896年:田端駅開業
・1901年:品川線と建設中の豊島線を統合、山手線に改名
・1902年:目白~板橋間に池袋信号所を開設
・1903年:池袋~田端間が開業、池袋信号所は池袋駅に昇格
池袋~田端間の路線は、赤羽駅で接続していた上野方面と品川方面の路線を南側でつなぐ目的で建設された。都市の成長予測や将来的な利用者確保といった戦略が随所に反映されており、線路敷設の決定ではないことが分かる。1925(大正14)年に環状運転が開始されるまで、都市の成長と鉄道計画は互いに影響を与え合いながら進化していった。
鉄道計画の背景には、地形条件、人口分布、将来の都市発展、既存交通網との接続など、多面的な判断があったことがうかがえる。池袋駅設置の決断は、当時の都市計画者と鉄道会社が、便宜や短期的利益ではなく、長期的な都市戦略を見据えた意思決定を積み重ねた結果であった。駅の位置は、都市の未来を映す戦略的選択であったといえる。