トヨタグループの相次ぐ不正は“日本の歪み”そのものだ 「現場との断絶」「セクショナリズム」、第三者委の調査書を改めて読む
日野自動車:意識の断絶とセクショナリズム
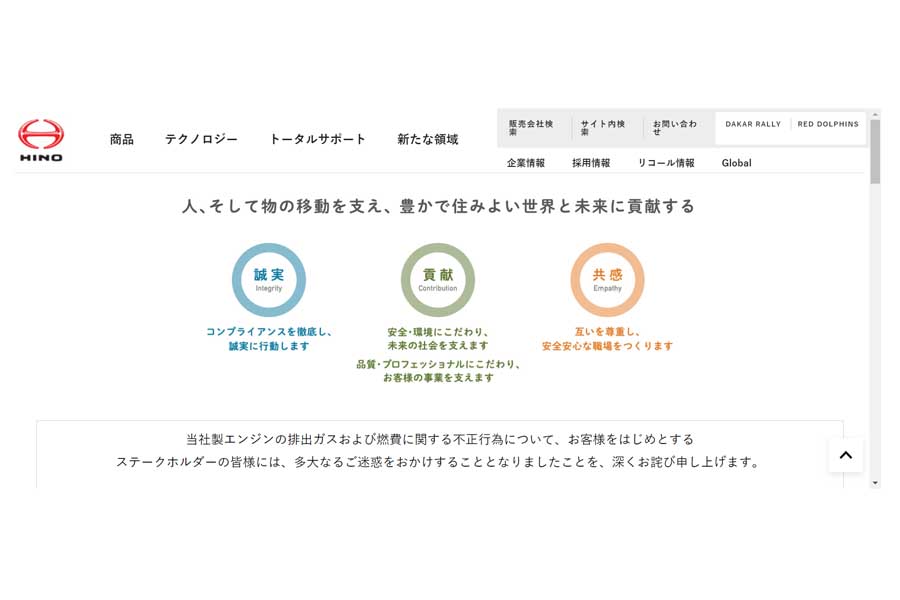
日野自動車は、2022年3月に、日本市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請において不正行為を確認したと公表。なお、日野自動車とトヨタ自動車との関係は、1966(昭和41)年に業務提携、2001(平成13)年に日野自動車株の過半を取得し子会社化という経緯をたどっている。
不正を行ったのは、認証申請のための劣化耐久試験や測定を行うパワートレイン実験部で、数値の書き換えや有利に働くように諸元値にげたを履かせるなどした。
調査委員会は、調査の初期の過程で「全役職員一丸となって、全体感あるクルマづくりを行なっていない」と感じたそうだ。具体的には、経営陣と現場の間に、クルマづくりを指示する側と指示される側という意識の断絶が生まれていたという。
さらには、セクショナリズムにより、不正の舞台となったパワートレイン実験部そのものや、担当者が孤立していた。パワートレイン実験部は開発の最終段階にあり、問題が発覚してももはやエンジン設計の見直しや車両全体のレイアウトの変更ができない状態だった。担当者にいたっては、課題を部に持ち帰っても、室長、部長、担当役員が課題解決のための頼れる相談相手になっていなかったとある。
また他部署の担当者は、セクショナリズムにより自部署に余計な課題を持ち帰らないという考えに陥っていたという。もちろんこれら以外にも、
・役員が必要以上に現場に口を出すため、現場が萎縮して判断や検討を放棄する体質
・「無理」を「可能」にしようとする現場の頑張りや献身性を上長が礼賛する風土
・問題を指摘するといったものが解決を指示される「いったもの負け」の風土
・マネジメントする仕組みの軽視
・不十分なチェック機能
・本来分離すべき開発業務と認証業務を同じ部署が担当
を報告書では指摘している。