トヨタグループの相次ぐ不正は“日本の歪み”そのものだ 「現場との断絶」「セクショナリズム」、第三者委の調査書を改めて読む
トヨタグループの不正行為の背景を再確認するため、豊田自動織機、ダイハツ工業、日野自動車の第三者委員会の調査報告書を改めて整理する。
ダイハツ工業:極度のプレッシャー下の現場担当者
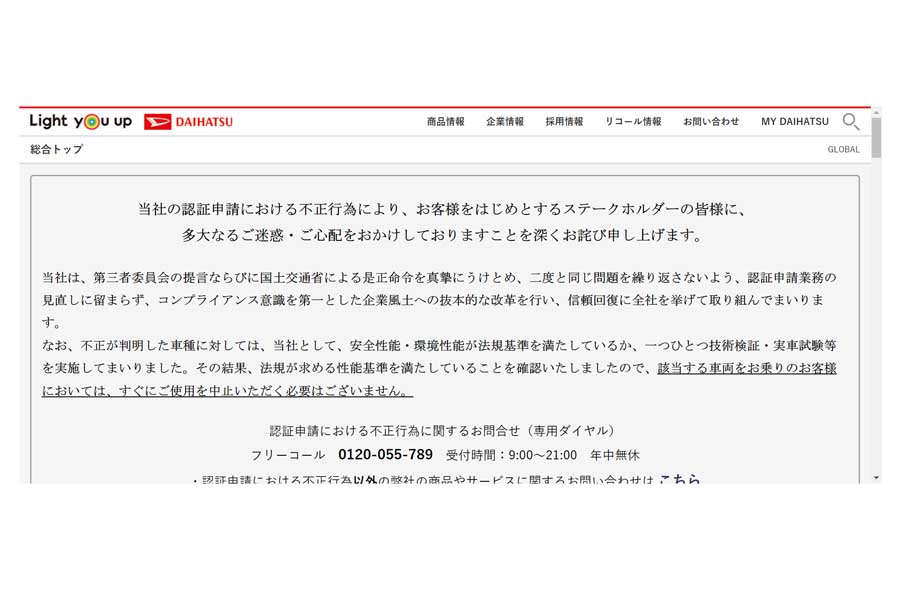
ダイハツ工業の場合、一番古いもので1989(平成元)年に不正行為が認められ、2014年以降の期間で不正行為の件数が増加していた。なお、ダイハツ工業とトヨタ自動車の関係は、1967(昭和42)年に業務提携を開始し、1998年にトヨタ自動車の子会社となり、2016年8月にトヨタ自動車の完全子会社となっている。
不正行為の直接的な原因やその背景については
・過度にタイトで硬直的な開発スケジュール
・現場任せで関与しない幹部
・チェック体制の不備
・法規の不十分な理解
・現場の担当者のコンプライアンス意識の希薄化
が挙げられている。
このほか、「自分や自分の工程さえよければよい」という組織風土が加わり、認証試験担当者へのプレッシャーや部門のブラックボックス化を促進したとある。
「現場任せで関与しない幹部」については、部長級以上の役職者が、現場レベルの不正行為を指示し、黙認したというような事実は見つからなかった。一方で、部長級以上の役職者が課題解決に関与しない体制により、「極度のプレッシャーに晒(さら)されて追い込まれた現場の担当者に問題の解決が委ねられた」という。
豊田自動織機の、「部長級に相談しても「何とかしろ」といわれる雰囲気がある」と似通っているといえよう。
この点について報告書では、一連の不正問題で「まずもって責められるべきは不正を行った従業員ではなくダイハツの経営幹部である」と断罪。
さらには、低コストで良質な自動車の短期開発は、営利企業である以上問題ないが、経営幹部のそれにともなうリスクや弊害を察知する感度が鈍かったと指摘している。