「クルマ + 向精神薬」に潜む運転リスク! 眠気・集中力低下の注意喚起も、矛盾する地方の現実 完全解決は“自動運転”の普及だ
向精神薬の添付文書には運転に注意するよう警告があり、一部の薬は運転を禁止している。ただし、実際には運転が必要な患者も多い。モビリティはこれを解決できるか。
だからといって無視するのも難しい
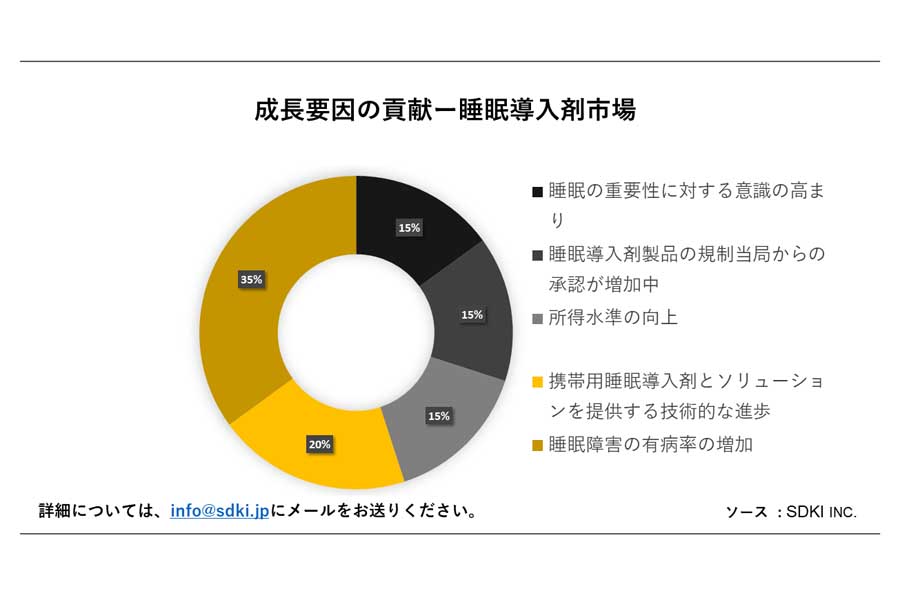
ではいっそ、気にしないで自動車運転をしていいものだろうか。
そういうわけにもいかない。なぜなら向精神薬はたいてい、飲み方や患者との相性次第で思わぬ障害やトラブルを引き起こす可能性を秘めているからだ。
例えば、担当医師が指定した以上の用量で向精神薬を飲んでしまったとき、何が起こるだろうか。普段は副作用がまったく出ていなかった向精神薬でも、用量をオーバーしてしまうと強烈な眠気やめまい、その他の異常に見舞われることは少なくない。そうしたときに自動車を運転するのは大変危険である。用量以上の内服可能性まで視野に入れるなら、やはり
「向精神薬は運転注意」
である。
のみならず、医師の指示したとおりの用量でさえ、それらが起こってしまうこともあり得る。睡眠薬でも抗うつ薬でも(疼痛対策に処方される)ガバペンチンでもそうだが、新しい薬を飲み始めた時期や用量を増やしたばかりの時期には、そうしたトラブルが発生しやすい。
飲み慣れた薬の場合でも、他の薬との飲み合わせや体調の良しあしによっては、いつになく眠気やめまいを感じるかもしれない。向精神薬を内服している人は、少しでも危ないと感じた場合、運転を一時的にストップし、担当医にそのことを相談すべきだろう。
そして睡眠薬をはじめとする、就寝前に内服し、睡眠にプラスの作用をもたらす薬の場合、翌日の運転に影響が出てしまう可能性が常についてまわる。翌日以降も血液中に薬が残っている可能性の高い向精神薬の場合は特にそうである。