なぜ国産旅客機「MRJ」は失敗したのか 現場技術者に非はなかった? 知られざる問題の本質とは
ホンダジェットは米国製

難航するMRJの傍らで小型ジェット機ホンダジェットの成功が各所で報じられたため、
「なぜ自動車メーカーのホンダが成功したのか」
という声も多く聞かれた。しかしホンダジェットは日本の国産機ではない。製造会社は米国のノースカロライナにあるHonda Aircraft Companyという会社であり、米国で設計開発された正真正銘米国製の飛行機なのだ。
日本で開発したのでは外国で売る航空機はつくれないことを、ホンダは知っていた。また、ホンダが日本で航空機を製造するなら、JCABから航空機製造事業者の認定が新規に必要で、この審査に合格するのも大変だ。つまり、
「日本製ではない」
ことがホンダジェットの一番大きな成功理由だ。
もうひとつ興味深い存在として、中国製の旅客機C919がある。エアバスA320やボーイング737に競合するクラスの機体で、2022年に中国国内の航空会社に引き渡しが始まっている。C919はもちろん中国航空局の型式証明を受けているので、中国国内で商業運航が可能だが、FAAの型式証明は取得していない。開発元のCOMACは、あえて「FAAの型式証明を取得しない」選択をしたのだ。
C919がFAAの型式証明を取得しようとすれば、MRJと同様の困難に見舞われたかもしれないが、広大な国土を持つ中国は、国内だけでも十分な市場がある。米国の型式証明を必要としないのだ。
国家プロジェクトのあり方と航空機産業
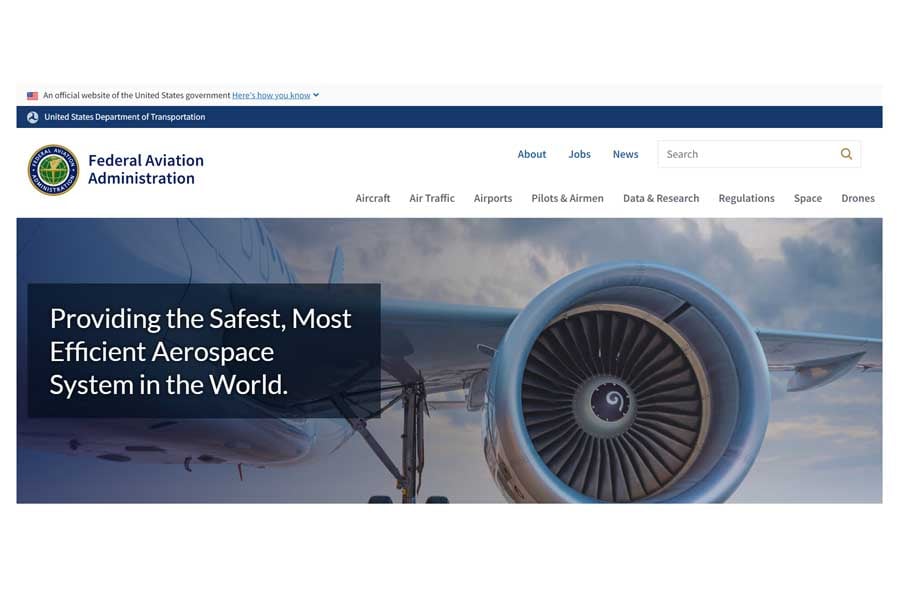
一方ではFAAの権威も揺れている。
ずさんな設計のために墜落が相次いだボーイング737MAXに関して、FAAによるボーイング社への審査が非常に甘かったことが調査で明らかになり、物議を醸している。FAAも神様ではないし、自国産業を保護したいという判断の存在も否めない。そのため、より安全な航空機の実現や、より自由で平等な国際市場の実現には、各国がオープンな場で情報を交換し、協力していくことが必要ではないか。
日本においても、経産省がプロジェクトを立ち上げる際、JCABの型式証明能力や、FAAの証明取得プロセスをどうするかといった問題が、十分に検討されたとは思えない。経産省とNEDOが実施したMRJに向けての技術研究は、高い付加価値を持つ製品実現のために必要な努力だが、日本の旅客機開発に困難をもたらす最重要課題は、こうした先端技術ではなく、
「国による認証制度」
の問題なのだ。
しかし、専門分野の研究や設計を担う現場技術者や、マーケットだけを見ている投資家や経営者では、こうした認識を持つのは難しい。特に日本では専門人材の流動性が低く、開発現場の実情から行政の制度までを、網羅的に知る機会は得にくい。
その結果、経産省/NEDOは市場や基礎研究だけを見て絵を描き、三菱はそれを足掛かりにして事業に取り組んだが、肝心の型式証明を手掛ける国交省は蚊帳の外という、驚くべき体制ができあがった。
これは「誰が悪い」という問題ではなく、国家プロジェクトのあり方や行政機関の整備方針など、日本という国の力が改めて問われるべき事例ではないだろうか。